- 戦国BANASHI TOP
- コラムの記事一覧
- 天下人の母・大政所「なか」の生涯とは?秀吉を支えた女性の実像に迫る
天下人の母・大政所「なか」の生涯とは?秀吉を支えた女性の実像に迫る
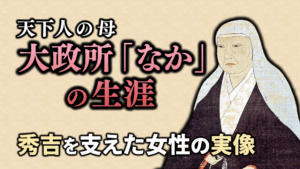
戦国時代、数多くの英雄たちが歴史の表舞台で活躍しました。その影には、彼らを支えた女性たちの存在があります。
今回は、豊臣秀吉の母として知られる大政所「なか」(仲、天瑞寺殿)にスポットを当て、その数奇な運命と知られざる素顔に迫りたいと思います。 一介の農民の妻から、天下人の母へ。彼女の人生は、まさにジェットコースターのようだったかもしれません。
大政所「なか」の謎多き出自と前半生
大政所、後の「なか」は、永正14年(1517年)に尾張国愛知郡御器所村(現在の名古屋市昭和区)で生まれたと言われています。
しかし、彼女の両親については諸説あります。
一つは、関鍛冶(刀鍛冶)の関兼員(または兼貞)の娘という説です。この説が正しければ、加藤清正の母や青木一矩の母とは姉妹ということになり、秀吉と彼らが従兄弟だったというのも納得がいきます。
もう一つは、『言経卿記』などの記録から、父は道円、母は妙円という人物だったとする説です。ただ、これは秀吉が自身の家系を飾るために、後から作られた話かもしれない、とも指摘されていて、実際のところは、はっきりとは分かっていません。まさに「歴史のミステリー」ですね。
その後、なかは木下弥右衛門という人物に嫁ぎます。 弥右衛門は織田信秀(信長の父)に仕える足軽組頭だったと言われています。
そして、二人の間には、後の瑞龍院日秀(秀吉の姉)と、あの豊臣秀吉が生まれます。
しかし、幸せな日々は長くは続かず、弥右衛門は秀吉が幼い頃に亡くなってしまったようです。
弥右衛門の死後、なかは竹阿弥という人物と再婚します。
そして、竹阿弥との間には、秀吉の片腕として活躍する豊臣秀長と、後に徳川家康に嫁ぐ朝日姫が生まれたとされています。
ただ、ここにも面白い説があり、歴史家の黒田基樹氏などは、最初の夫・弥右衛門と竹阿弥は同一人物で、弥右衛門が出家して竹阿弥と名乗ったのではないか、という説を提唱しています。
もしそうなら、日秀、秀吉、秀長、朝日姫は全員同じ父親の子供ということになります。想像が膨らむポイントですね。
息子の出世と「大政所」への道
ご存知の通り、息子の秀吉は織田信長のもとで頭角を現し、破竹の勢いで出世していきます。
それに伴い、母であるなかの人生も一変しました。
秀吉は長浜城主になると、母や妻のねね(北政所)を呼び寄せ、一緒に暮らすようになります。秀吉にとって、母は心の支えであり、非常に大切にしていたことがうかがえます。
天正13年(1585年)、秀吉が関白に就任すると、母なかには従一位の位と「大政所」の称号が朝廷から贈られました。
「大政所」とは、摂政や関白の母に与えられる敬称です。 一介の農民の出とも言われる女性が、最高の位と称号を得る。まさにシンデレラストーリー。ちなみにそれ以前は「二位尼君」などと呼ばれていたようです。
秀吉は、大坂城や聚楽第に母のための豪華な住まいを用意したと言われています。
病気がちだった母のために、秀吉が京都の大徳寺に寿塔(生前に建てる墓)を建て、その回復を祈ったという話は有名で、これが後の天瑞寺(大政所の法号「天瑞院」にちなむ)となりました。
この寿塔を覆っていた建物は、後に横浜の三溪園に移され、「旧天瑞寺寿塔覆堂」として現存し、重要文化財に指定されています。
歴史のターニングポイント・母、人質となる
大政所なかと言えば、歴史の教科書にも出てくるかもしれない有名なエピソードがあります。
それは、徳川家康を上洛させるための「人質」としての役割です。
小牧・長久手の戦いの後も、なかなか秀吉に臣従しようとしない家康。
業を煮やした秀吉は、妹の朝日姫を家康に嫁がせることで家康を従属させます。さらに天正14年(1586年)、正親町天皇の譲位式にあわせて家康に上洛・出仕命令を出し、その代わりに実の母である大政所を家康のいる岡崎へ送るという策に出ます。当時、主従関係が成立した後、はじめて出仕する際には進退保障として人質を出すのが通例でした。
つまり、表向きは「娘の朝日姫に会うため」でしたが、実質的には人質でした。
天下人の母が、敵対するかもしれない相手の本拠地へ赴く。これは相当な覚悟が必要だったでしょう。
岡崎では、大政所の屋敷の周りに薪が積まれ、「もし家康公の身に何かあれば、大政所様にもご覚悟を」という徳川方の物々しい雰囲気だった、なんて話も伝わっています。まさに一触即発ですね。
この大政所の岡崎滞在と、秀吉の粘り強い交渉の結果、ついに家康は上洛しました。
大政所は、まさに日本の歴史が大きく動くきっかけを作ったと言えるかもしれません。
数ヶ月ほど岡崎に滞在した後、無事に大坂へ戻りました。
この時、自分に親切にしてくれた家康の家臣・井伊直政には褒美を、厳しい態度だった本多重次(作左衛門)には罰を、と秀吉に頼んだという逸話も残っています。
真偽は定かではありませんが、彼女の気性や影響力を示すエピソードとして興味深いですね。
謎と論争・フロイスの記録と異説
大政所や秀吉の出自に関しては、いくつかの謎や、ちょっとダークな説も存在します。
宣教師ルイス・フロイスの著書『日本史』には、興味深い記述があります。
フロイスによると、伊勢の国から秀吉の弟だと名乗る若者が現れましたが、秀吉は大政所に確認。
大政所は「そのような子は産んだ覚えはない」と否定し、結局その若者は処刑されてしまった、というのです。
また、フロイスは秀吉には他にも貧しい農民の姉妹が尾張にいた、とも記しています。
これらの記述から、歴史家の服部英雄氏などは、秀吉は自身の低い出自や、母の複雑な過去(例えば、3回以上の結婚歴があったなど)を隠すために、不都合な兄弟姉妹を抹殺したのではないか、という大胆な説を提唱しています。
秀吉の出自が「河原ノ者・非人」といった被差別階層にあったとする説も、この服部氏の研究から出ています。
これらの説は非常に衝撃的で、まだ論争の的ではありますが、秀吉の異常なまでの出世欲や、出自に対するコンプレックスを考えると、一概に否定できない何かを感じさせます。
ただし、これらはあくまで「説」であり、確定的な証拠があるわけではありません。
歴史の記録は、勝者の側から書かれることも多いですから、真相は闇の中かもしれませんね。
晩年と最期、そして母の面影
大政所は、子供たちの行く末を案じながら晩年を過ごしたようです。
天正18年(1590年)には娘の朝日姫が、翌天正19年(1591年)には息子の秀長が相次いで亡くなり、心痛は大きかったことでしょう。
秀吉が朝鮮出兵(文禄の役)のために名護屋へ赴こうとした際には、病身を押して止めようとしたとも伝えられています。
そして、文禄元年(1592年)7月22日、聚楽第で77年の生涯を閉じました。
秀吉の悲しみは深く、母の亡骸に取りすがって泣き崩れたと言われています。
大政所の墓所は、京都の大徳寺塔頭・天瑞寺にあります。
また、高野山の奥之院や、京都の本圀寺にも供養塔や墓石が存在します。
彼女の姿を伝える肖像画も残されており、慶長20年(1615年)に描かれたとされるものが大徳寺にあります。
その賛(絵に添えられた言葉)には、「黒衣青帽の老婆禅、百八の念珠を右辺に提ぐ。美誉芳声は捴て閑事、胸中天雲破れて月孤圓なり」とあり、仏門に帰依した穏やかな姿と、世俗の名声を超越した境地が偲ばれます。
まとめ
大政所なか。
その生涯は、息子の出世と共に大きく揺れ動き、日本の歴史にも深く関わりました。
出自の謎、人質としての役割、そして天下人の母としての栄光と苦悩。
彼女の人生を知ることは、豊臣秀吉という人物を、そして戦国という時代をより深く理解するための一つの鍵となるのではないでしょうか。
記録が多くない分、想像を掻き立てられる存在でもあります。
皆さんも、彼女の生きた時代に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。








