- 戦国BANASHI TOP
- コラムの記事一覧
- 豊臣秀長の正妻「慶(けい)」戦国乱世から江戸初期を生き抜いた女性
豊臣秀長の正妻「慶(けい)」戦国乱世から江戸初期を生き抜いた女性
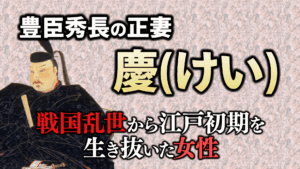
豊臣秀吉の天下統一事業において、弟・豊臣秀長は「賢弟」「良弼」と称され、その冷静沈着な判断力と卓越した政治・軍事能力で兄を支え続けた、まさに屋台骨とも言える存在でした。
その秀長の正妻であった「慶(けい)」こと慈雲院(ちうんいん)は、夫である秀長や義兄・秀吉、あるいは他の戦国時代の女性たちのように歴史の表舞台で華々しく活躍する機会こそ多くありませんでしたが、戦国乱世から江戸時代初期という激動の時代を生き抜き、特に夫の死後に見せた深い信仰心と行動は、彼女の人物像を今に伝えています。
2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で、俳優の吉岡里帆さんが彼女の役を演じることが発表されて以降、その生涯と人物に対する関心が高まっています。
本記事では、慈雲院(慶)の人物像と、豊臣家における彼女の足跡、そして彼女が生きた時代の背景について、信頼性の高い史料に基づき、より深く掘り下げて解説します。
目次
慈雲院の出自と秀長との結婚 –謎に包まれた前半生–
慈雲院の生年や彼女がどのような家の出身であったかなど、その出自に関する正確な史料は極めて乏しく、謎に包まれているのが現状です。
一部の歴史解説サイトなどでは「秋篠伝左衛門の娘」であるといった記述も見受けられますが、これは別妻・摂取院の出自であり、正妻・慈雲院の出自は不明である。
当時の武家の女性、特に傍流の家臣の妻や娘の出自が詳細に記録されることは稀であったため、慈雲院もその例に漏れないと考えられます。
彼女がいつ、どのような経緯で豊臣秀長(当時は羽柴小一郎秀長)に嫁いだのか、その具体的な時期や経緯もまた、明確にはわかっていません。しかし、天正13年(1585年)9月、秀長が兄・秀吉から大和国(現在の奈良県)と和泉国の一部を与えられ、大和郡山城に入城した際のことと考えられます。
興福寺の僧侶の日記である『多聞院日記』には、「羽柴大和守(秀長)の御にょうぼ(女房)が、見事な輿に乗って郡山に到着した」という旨の記述があります。
この「御にょうぼ」が慈雲院を指している可能性が非常に高く、この頃には彼女が秀長の正妻としてその傍らにいたことがうかがえます。
秀長はこの時、従五位下・大和守に叙任されており、彼女もまた「大和守の奥方」としての新たな生活を大和郡山でスタートさせたことになるでしょう。
夫・秀長の栄光とその陰で –大和大納言の正妻として–
豊臣秀長は、兄・秀吉が織田信長の一武将であった時代から常に兄を補佐し、その温厚篤実な人柄と実務能力の高さから、多くの武将や家臣からの信頼も厚い人物でした。
秀吉の天下一統事業が本格化すると、秀長はその右腕として紀州攻め、四国攻め、九州攻め、小田原攻めといった主要な合戦で大将・副将格として軍を率い、戦功を挙げる一方で、占領地の統治や戦後処理においてもその手腕を発揮しました。
特に九州平定後には、日向国(現在の宮崎県)を与えられ、その統治にも尽力しました。その後、秀吉の関白就任に伴い、秀長もまた破格の昇進を遂げ、天正15年(1587年)には従二位・権大納言にまで昇り、「大和大納言」と尊称される大大名となりました。その所領は最終的に大和・和泉・紀伊の三国にまたがり、100万石を超えるとも言われる広大なものでした。
秀吉は感情の起伏が激しい一面がありましたが、秀長はその冷静さで兄を諫め、豊臣政権内部の調整役としても極めて重要な役割を担っていたのです。秀吉が唯一本音で相談でき、時には叱責すら受け入れたのが秀長であったと言われています。
慈雲院は、この日本有数の実力者である大和大納言の正妻として、どのような日々を送っていたのでしょうか。
残念ながら、彼女自身の具体的な行動や政治的な発言を記した史料はほとんど残されていません。しかし、大名の正妻は、単に夫の身の回りの世話をするだけでなく、広大な屋敷の切り盛り、多くの侍女や家臣たちの管理、さらには他の大名家との交際や情報交換など、多岐にわたる重要な役割を担っていました。
特に秀長は温厚で人望が厚かったとされますから、その家庭もまた、慈雲院によって円満に保たれていたと想像されます。彼女は、栄華を極める夫を内助の功で支え、豊臣家の一翼を担う大和大納言家の奥を取り仕切っていたと考えられます。
夫・秀長の死と慈雲院の深い信仰心 –高野山への祈り–
天下の副将軍とまで評された豊臣秀長でしたが、天正19年(1591年)1月22日、病により大和郡山城でこの世を去ります。享年52歳(満50歳)。
この秀長の死は、豊臣秀吉にとって精神的にも政権運営上も計り知れないほどの大きな痛手となりました。
秀吉はその死を深く悼み、秀長の不在がその後の豊臣政権の舵取りに微妙な、しかし確実な影響を与えたとも言われています。
秀吉の晩年の政策(例えば朝鮮出兵や豊臣秀次事件など)における強硬化や判断の揺らぎは、秀長という優れた諫言役・調整役を失ったことと無縁ではないとする歴史家も少なくありません。
夫の死後、慈雲院がどのような心境で日々を過ごしたか、詳細は不明ですが、彼女が深い信仰の道に入ったことは、その後の行動から明らかです。
彼女の信仰心の篤さを示す最も重要な事績が、高野山奥之院における彼女自身の供養塔の建立です。
秀長の死からわずか132日後、すなわち天正19年5月7日という早い段階で、慈雲院は自身の「逆修供養塔(ぎゃくしゅうくようとう)」を高野山奥之院の豊臣家墓所内に建立しました。「逆修」とは、生前にあらかじめ自身の死後の冥福を祈って仏事を行い、供養塔などを建てることを指します。これは当時の武家社会において、特に女性の間で見られた篤い信仰の一つの形でした。
高野山大学総合学術機構紀要に掲載された木下浩良氏の研究論文「高野山奥之院の豊臣家墓所の石塔群」によれば、この慈雲院の逆修供養塔である五輪塔には、基礎部分に「大納言殿北方慈雲院 芳室紹慶 逆修 天正十九年五月七日」という銘文がはっきりと刻まれています。
「北方(きたのかた)」とは正妻を意味し、「慈雲院芳室紹慶(じうんいんほうしつしょうけい)」が彼女の戒名(法号)であったことがわかります。また、この五輪塔は砂岩製で、高さ約193cmと、当時の女性の供養塔としては比較的大きく、堂々とした風格を備えています。
注目すべきは、この慈雲院の供養塔が、同じく高野山奥之院に築かれた夫・秀長の供養塔(こちらは秀長の死後に建立された追善供養塔)と様式や材質が酷似しており、同じ石工によって、ほぼ同時期に造立された可能性が高いと指摘されている点です。
秀長の供養塔の銘文には秀長の没年月日である「天正十九年正月廿二」が刻まれています。これらのことから、慈雲院が夫・秀長の百か日法要などを区切りとして、夫の供養塔を建立するとともに、自身の逆修供養塔をも建立し、夫への深い愛情と追悼の意、そして自身の来世への願いを形として残したと推測されます。
この一連の行動は、彼女の信仰心の深さだけでなく、困難な状況における意志の強さと行動力を示していると言えるでしょう。
慈雲院の子供たちと秀長家の終焉 –血筋の行方–
慈雲院と秀長の間には、史料によれば男子の小一郎(与一郎とも呼ばれた)がいたとされていますが、残念ながら早くに亡くなった(夭折した)と伝えられています。当時の乳幼児死亡率の高さから、病などによるものであったと考えられます。
娘については、二人の存在が確認されています。
一人は周防国(現在の山口県東部)の有力大名である毛利輝元の従弟であり養嗣子となった毛利秀元に嫁いだ大善院(だいぜんいん、通称おきく)です。彼女は秀吉の養女として毛利家に嫁ぎ、慶長14年(1609年)に22歳で亡くなっています。
もう一人の娘はおみやといい、秀長の養子で甥にあたる豊臣秀保(とよとみのひでやす、羽柴秀保)に嫁ぎました。
これらの娘たちの実母が慈雲院であったかどうかについては、史料によっては秀長の別妻であった摂取院(せっしゅいん、興俊尼・光秀尼とも)の子とする説もあり、断定はできません。しかし、正妻である慈雲院が養育に関わった可能性は高いでしょう。
秀長の死後、その広大な遺領と家督を継いだのは、この養子であり娘婿でもあった豊臣秀保でした。秀保はまだ若く、兄である秀勝(後の岐阜中納言)の後見を受けたとされます。
しかし、その秀保もまた、文禄4年(1595年)4月、わずか17歳という若さで、朝鮮出兵の陣中で病没(一説には自刃とも)してしまいます。
この秀保の早すぎる死により、「大和大納言家」とも称された豊臣秀長の家系は、悲劇的にも断絶してしまうことになりました。
慈雲院は、夫・秀長に先立たれ、さらにその家を継いだ秀保の夭折によって、豊臣一門の有力な支えであった秀長家の終焉を目の当たりにするという、さらなる悲運に見舞われたのです。
慈雲院の晩年と「慶」という呼称の由来
秀長の死後、そして秀保の死による大和豊臣家の終焉の後も、慈雲院は歴史の片隅で静かに生き続けました。
彼女の晩年に関する史料は多くありませんが、特筆すべきこととして、関ヶ原の戦いを経て天下人となった徳川家康から、大和国において2千石の化粧料(隠居料や生活費に充てるための所領)を与えられていたことが記録に残っています。
これは、かつての豊臣政権の重鎮であった秀長の正妻として、また豊臣家の一族として、新政権である江戸幕府からも一定の敬意と配慮が払われていたことを示しています。
彼女の後半生は、この所領からの収入によって支えられていたと考えられます。
慈雲院がいつ亡くなったのか、その正確な没年月日は不明です。
しかし、彼女に与えられていた大和国内の2千石の所領が、元和年間(1615年~1624年)のいずれかの時期に幕府の直轄領(天領)になっていることから、この元和年間のうちに彼女が亡くなったと推測されています。
彼女の墓所がどこにあるのかも、現在のところ特定されていません。高野山の供養塔はあくまで生前に建てられた逆修塔であり、彼女の遺骨がそこに納められたかどうかは定かではありません。
近年、特に2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」の役名として「慶(けい)」という名前が慈雲院(に相当する人物)に用いられていることで、この「慶」という呼称が注目されています。
前述の通り、高野山の供養塔の銘文には彼女の法号として「芳室紹慶」と刻まれていました。この「紹慶」の一字「慶」をとって、現代において彼女の呼び名として、あるいはドラマの役名として採用されたと考えるのが最も自然な解釈です。
当時の高貴な女性の本名(諱)が公の記録に残ることは極めて稀であり、「慶」という名前が彼女の生前の実名であったという確証はありません。歴史上の人物として彼女を指す場合は、やはり史料で確認できる慈雲院、あるいは慈雲院芳室紹慶といった法名を用いるのがより正確と言えるでしょう。
まとめ –歴史の陰で輝いた女性の生き様–
慈雲院(慶)は、豊臣秀吉の天下取りを実質的に支えた「もう一人の豊臣」とも言える豊臣秀長の正妻として、夫の栄光の時代を共に過ごし、その死後は深い信仰心をもって菩提を弔い、激動の時代をしなやかに生き抜いた女性でした。
彼女自身の言葉や具体的な行動を伝える史料は限られていますが、高野山奥之院に現存する彼女の逆修供養塔は、夫への変わらぬ想い、篤い信仰心、そして自らの来世への願いを込めた、まさに彼女の「生きた証」とも言える貴重な歴史遺産です。
歴史の表舞台で華々しい活躍を見せることはなくとも、慈雲院のように、時代の転換期を力強く生き、家族を支え、自らの信仰を守り抜いた女性たちが数多く存在しました。
彼女の生涯は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武家の女性が置かれた立場や、その精神世界の一端を私たちに垣間見せてくれます。
豊臣秀長という偉大な夫の陰に隠れがちではありますが、慈雲院の生き様は、歴史の中で静かに、しかし確かな存在感をもって輝いていた一人の女性の姿として、今後もより多くの人々に知られ、語り継がれていくに違いありません。








