- 戦国BANASHI TOP
- 歴史的建造物の記事一覧
- 上田城 – 真田昌幸の難攻不落の名城と徳川軍撃退の歴史
上田城 – 真田昌幸の難攻不落の名城と徳川軍撃退の歴史
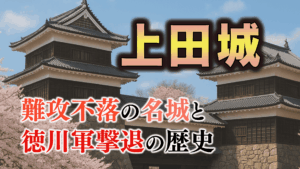
長野県上田市に聳える上田城は、戦国時代の名将真田昌幸が築いた平城で、徳川の大軍を二度にわたり撃退した「難攻不落の城」として日本史に名を刻んでいます。千曲川と矢染川が作る河岸段丘という天然の要害を巧みに活用し、最小の普請で最大の防御効果を実現した真田流築城術の傑作として、現在でも多くの歴史愛好家が訪れる名城です。
目次
上田城の歴史 – 真田氏の築城と戦略的立地
真田昌幸の築城と地形活用戦略
天正11年(1583年)、真田昌幸は千曲川と矢染川が作る河岸段丘の突端という絶好の立地に上田城を築城しました。この城は、昌幸が徳川氏に従属していた時に対上杉氏の防衛拠点として家康に築かせた城で、その後、上杉氏に寝返り、今度は対徳川氏の防衛拠点になった城です。丸島和洋『図説 真田一族』戎光祥出版 2015年南側の断崖「尼ヶ淵」や西の矢染川を天然の外堀として活用し、わずかな普請で堅固な要塞を完成させる昌幸の戦略眼は、後の徳川軍撃退の基盤となりました。
昌幸の築城思想は、当時の流行建築も押さえていました。近年、発掘調査によって、金箔の瓦が出土しました。これは織豊期の城郭の特徴で、天正13年(1585年)に豊臣秀吉に従属した際にほどこされたものであった可能性が高いです。このように上田城は、織豊期の流行建築も取り入れた側面もありました。丸島和洋『図説 真田一族』戎光祥出版 2015年
また、単なる防御施設の建設にとどまらず、城下の坂道や動線設計にまで及びました。敵の移動や展開を抑制する「地取り」の技術により、数的劣勢を地形的優位で補う仕組みを構築したのです。東虎口に置かれた「真田石」などの巨石は、敵に対する視覚的・心理的な威圧効果も狙った演出でした。
破城から再興へ – 仙石氏と松平氏の時代
慶長5年(1600年)の関ヶ原合戦後、真田氏は改易となり、上田城は破城令により建物が破却され、堀も埋め立てられました。しかし元和8年(1622年)、小諸から仙石忠政が移封されると城郭の再興が始まり、寛永3年(1626年)には仙石氏による新たな上田城が完成しました。
その後、仙石氏はお家騒動により改易され、**宝永3年(1706年)**に松平氏が入封し、以後明治維新まで城主を務めました。松平氏時代には藩校「明倫堂」が設置され、教育・人材育成の拠点としての役割も担いました。明治維新後の払い下げにより多くの建物が取り壊されましたが、幸いにも西櫓は現存し、現在は長野県宝に指定されています。
上田合戦 – 徳川軍を二度撃退した奇跡
第一次上田合戦(天正13年・1585年)- 真田2,000 vs 徳川7,000
天正13年(1585年)8月、徳川家康は真田昌幸の上田城攻略を命じ、鳥居元忠、大久保忠世らが率いる7,000余の大軍が上田に進軍しました。対する真田方はわずか2,000足らずの兵力でしたが、昌幸は地形を最大限に活用した巧妙な戦術で徳川軍を迎え撃ちました。
昌幸の作戦は、城外での消耗戦と奇襲攻撃の組み合わせでした。千曲川と矢染川に挟まれた段丘地形により敵の展開を制限し、虎口での集中防御と城外での遊撃戦により、数的劣勢を戦術的優位に転換したのです。この戦いで徳川軍は1300人も撃たれる大きな損害を被り、上田城攻略を断念せざるを得ませんでした。真田の名は一躍天下に知れ渡り、「表裏比興」と呼ばれる昌幸の戦略的柔軟性が証明された歴史的合戦となりました。
補足:上杉景勝は援軍として、北信濃国衆に陣触れを出し、通常では動員対象にならない
15歳以下の少年と60歳以上の老人まで動員し、戸石城近くまで進出した。丸島和洋『図説 真田一族』戎光祥出版 2015年
第二次上田合戦(慶長5年・1600年)- 秀忠遅参の原因
慶長5年(1600年)9月、関ヶ原合戦直前に再び上田城攻防戦が勃発しました。今度は徳川秀忠が率いる軍勢が中山道を進軍中、真田父子が立て籠もる上田城の攻略に7日間を費やす結果となりました。この遅延により秀忠軍は関ヶ原本戦に間に合わず、家康から厳しく叱責されることとなりました。
この時、真田家は巧妙な分立戦略を採用していました。父の昌幸と次男の信繁(幸村)は西軍に、長男の信之は東軍に与することで、どちらが勝利しても真田家の血脈を残せる体制を整えていたのです。結果的に東軍が勝利し、信之の系統が大名として存続することになりました。
アクセス情報 – 上田城への交通手段
電車でのアクセス
上田城跡公園へは、JR北陸新幹線・しなの鉄道・上田電鉄別所線が乗り入れる上田駅が最寄り駅となります。駅から城跡までは徒歩約12分の距離で、駅前から北に向かって歩けば到達できます。新幹線を利用すれば、東京駅から上田駅まで約1時間30分でアクセス可能です。
路線バス利用
上田駅からは上田市街地循環バス「あかバス」(赤運行)を利用することもできます。「公園前」バス停で下車すれば城跡入口まですぐです。運賃は200円で、本数も比較的多く運行されています。
自動車でのアクセス
自動車の場合は、上信越自動車道の上田菅平インターチェンジから約4キロメートル、所要時間約15分で到達できます。中央自動車道からの場合は、岡谷ジャンクションで長野自動車道に入り、更埴ジャンクションで上信越自動車道に乗り換えて上田菅平インターを目指します。
駐車場について – 重要な注意事項
城跡公園内の駐車場は全て有料です。普通車用は北駐車場(通常222台、工事により令和8年8月まで189台)と南駐車場(85台)があります。料金体系は通常期と特別期(桜・ゴールデンウィーク・紅葉シーズン)で異なります。
通常期は入庫後1時間無料、以降1時間100円、当日上限500円です。特別期は入庫後3時間500円、以降1時間100円、当日上限1,000円となります。バス・大型車は専用の「上田城跡バス駐車場」を予約制(1日2,000円)で利用する必要があります。二輪車は北・南駐車場への入場ができませんが、バス駐車場内の二輪スペースを無料で利用できます。
見どころ – 現存建造物と復元された城郭
現存する西櫓(長野県宝)
上田城で唯一現存する建造物が西櫓です。仙石氏時代の寛永年間(1624-1644年)に建設されたと推定され、現在は長野県宝に指定されています。二重二階の櫓建築で、戦国期から江戸初期の築城技術を今に伝える貴重な遺構です。ただし、内部は非公開となっており、外観のみの見学となります。
復元された南櫓・北櫓
南櫓と北櫓は明治期に城外の遊郭に移築されていましたが、昭和24年(1949年)に市民の熱意により城内に戻されました。現在は内部が展示室として活用され、真田氏の歴史資料や城郭関連の展示を見学することができます。櫓からは上田市街や千曲川の眺望も楽しめます。
東虎口櫓門(平成6年復元)
本丸への正面入口である東虎口には、平成6年(1994年)に復元された櫓門があります。発掘調査の成果に基づいて江戸時代の姿を忠実に再現しており、真田時代の「真田石」と呼ばれる巨石と組み合わせて、往時の威容を偲ぶことができます。
眞田神社 – 歴代城主を祀る城鎮守
本丸跡には眞田神社が鎮座しています。もともとは松平神社として創建されましたが、戦後に真田・仙石・松平の歴代城主を合祀して上田神社となり、昭和38年(1963年)に眞田神社に改称されました。真田家ゆかりの御朱印や絵馬なども授与され、多くの参拝者が訪れています。
上田市立博物館と櫓見学
本丸内には上田市立博物館があり、上田地方の歴史・文化・自然に関する展示が充実しています。開館時間は9:00から17:00(最終入館16:30)、観覧料は博物館と櫓のセット券が一般500円、単独券は各300円です。櫓内部では真田氏関連の資料展示が行われており、上田城の歴史を詳しく学ぶことができます。
周辺観光 – 真田ゆかりの地と信州の名所
真田氏歴史館と真田の里
上田市真田町には真田氏歴史館があり、真田昌幸・信幸・幸村三代の詳細な資料が展示されています。真田氏発祥の地として、真田氏本城跡(山城)や真田氏館跡(御屋敷公園)も整備されており、真田氏のルーツを辿ることができます。特に御屋敷公園は春のツツジの名所としても知られています。
真田氏本城跡は真田三代の本拠となった山城で、現在も石垣や曲輪の遺構が良好に保存されています。ただし、工事等により通行止めとなる期間があるため、事前に上田市や観光協会のホームページで確認することをお勧めします。
別所温泉 – 信州最古の温泉地
上田城から南東約15キロメートルに位置する別所温泉は、信州最古の温泉地として1,000年以上の歴史を誇ります。「信州の鎌倉」とも呼ばれる古刹の里で、温泉街には国宝・重要文化財級の寺院が点在しています。
安楽寺八角三重塔(国宝)
別所温泉の安楽寺には、日本唯一の木造八角塔である八角三重塔(国宝)があります。年輪年代法による調査により、1290年代(材の伐採年1289年)の建立と判明し、宋様式の禅宗建築として極めて貴重な遺構です。鎌倉時代の建築技術の粋を集めた傑作として、建築史上重要な価値を持っています。
戸隠神社 – 信州を代表する古社
長野市の戸隠神社は、奥社・中社・宝光社・九頭龍社・火之御子社の五社から成る信州を代表する古社です。上田城からは車で約1時間の距離にあり、特に奥社への参道は樹齢400年以上の杉並木が続く神秘的な空間として人気です。戸隠そばの発祥地としても知られ、参拝と合わせて信州グルメを楽しむことができます。
四季の上田城 – イベントと見頃情報
千本桜まつりと春の魅力
上田城跡公園は「日本さくら名所100選」に選定される桜の名所でもあります。毎年4月上旬から中旬にかけて「千本桜まつり」が開催され、ソメイヨシノやシダレザクラなど約1,000本の桜が園内を彩ります。2025年は4月5日から16日まで開催され、ライトアップは4月20日まで延長予定です。
秋の紅葉まつり
秋には「上田城紅葉まつり」が開催され、モミジやイチョウの美しい紅葉を楽しむことができます。2025年は11月8日・9日に開催予定で、武者行列や太鼓演奏などの催し物も企画されています。
まとめ – 真田の魂が息づく名城
上田城は、真田昌幸の卓越した戦略眼と築城技術、そして二度の徳川軍撃退という輝かしい戦歴により、日本城郭史上特別な地位を占める名城です。現在も残る石垣や復元された櫓群、そして真田氏ゆかりの史跡群は、戦国時代の息吹を現代に伝える貴重な文化遺産となっています。
信州上田の豊かな自然と歴史文化に包まれた上田城は、歴史愛好家のみならず、日本の伝統文化に触れたい全ての人々にとって価値ある体験を提供してくれるでしょう。春の桜、夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色と、四季を通じて異なる表情を見せる上田城への訪問は、きっと忘れがたい思い出となるはずです。



