- 戦国BANASHI TOP
- 歴史的建造物の記事一覧
- 【完全ガイド】武田氏館(躑躅ヶ崎館)のすべて – 信玄・三代の栄光と戦いの舞台を巡る旅
【完全ガイド】武田氏館(躑躅ヶ崎館)のすべて – 信玄・三代の栄光と戦いの舞台を巡る旅
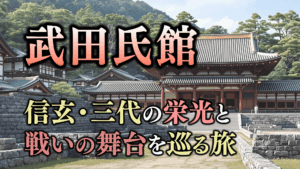 山梨県甲府市に位置する武田氏館跡、通称「躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)」。ここは戦国時代の名将・武田信玄とその一族が三代、約60年間にわたって本拠地とした場所です。甲斐統一の拠点として、そして数々の歴史的な戦いの司令塔として、日本の戦国史にその名を刻みました。
山梨県甲府市に位置する武田氏館跡、通称「躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)」。ここは戦国時代の名将・武田信玄とその一族が三代、約60年間にわたって本拠地とした場所です。甲斐統一の拠点として、そして数々の歴史的な戦いの司令塔として、日本の戦国史にその名を刻みました。
現在は武田信玄公を祀る武田神社の境内となり、国史跡として大切に保護されています。この記事では、武田氏館の歴史、戦いの舞台裏、現存する遺構の見どころ、最新のアクセス情報から周辺の関連史跡まで、その魅力を余すところなくご紹介します。
目次
歴史 – 武田三代63年間の興亡
武田信虎による築城と甲斐統一
躑躅ヶ崎館の歴史は、永正16年(1519年)、武田信虎によって築かれたことに始まります。信虎は、従来の石和館から本拠地を移し、相川の扇状地に位置するこの地に新たな館を構えました。背後には詰城(つめのしろ)である要害山城を控え、平時と戦時の両方に対応できる戦略的な立地でした。
信虎はこの館を拠点に、甲斐国内に割拠していた有力国衆との抗争を制し、甲斐国統一を成し遂げます。館の周囲には家臣団の屋敷が建ち並び、濠と土塁で防御された一大政治都市を形成。天文10年(1541年)まで22年間天正9年(1581年)までの62年間、この館は甲斐国の政治・軍事の中枢として機能し、武田氏発展の礎を築きました。
武田信玄の時代 – 勢力拡大の司令塔
天文10年(1541年)、父・信虎を駿河へ追放した武田信玄(当時は晴信)が家督を継承すると、躑躅ヶ崎館は武田氏最盛期の象徴となります。信玄はこの館を30年間にわたり拠点とし、信濃、駿河、西上野へと次々に侵攻し、その勢力を飛躍的に拡大させました。
館は単なる居館から、戦略的な司令塔へとその役割を変えます。館内には信玄の中心的な居住区のほか、嫡男・義信のために築かれた西曲輪、食糧庫とされる味噌曲輪、大井夫人の隠居所と伝わる御隠居曲輪などが設けられ、拡張されていきました。「風林火山」の軍旗のもと、情報収集、軍事会議、外交交渉がここで行われ、武田氏の威信を天下に示しました。
重要ポイント: 信玄は躑躅ヶ崎館を30年間使用し、この間に甲斐国から信濃、上野、駿河へと勢力を拡大。館は武田氏最盛期の象徴的存在となりました。
武田勝頼時代と館の終焉
元亀4年(1573年)に信玄が没すると、四男の勝頼が家督を継承。勝頼もこの館を本拠としましたが、天正3年(1575年)の長篠の戦いでの大敗を機に、武田氏の勢力は陰りを見せ始めます。
織田・徳川連合軍の圧迫が強まる中、勝頼は天正9年(1581年)、より防御に優れた新府城(韮崎市)へ本拠地を移転する決断を下します。この際、躑躅ヶ崎館は一時的に破却されました。しかし、翌天正10年(1582年)3月、織田信長による甲州征伐により武田氏は滅亡。63年間にわたる武田氏の本拠地としての歴史は、ここに幕を閉じたのです。
近世以降の変遷と武田神社の創建
武田氏滅亡後、館跡は甲斐統治の拠点として河尻秀隆(織田家臣)、徳川家康、浅野長政・幸長父子(豊臣家臣)らによって再利用されました。しかし、甲府城が築かれると政治的機能はそちらへ移ります。
江戸時代を通じて武田氏ゆかりの地として保存され、大正8年(1919年)、武田信玄を御祭神とする武田神社が創建されました。昭和13年(1938年)には国史跡に指定され、戦国時代の貴重な遺構として現在に至るまで多くの人々に親しまれています。
戦い – 甲斐の拠点から見た戦国史
甲斐国統一拠点としての役割
躑躅ヶ崎館は、信虎による甲斐国統一戦争の中心拠点でした。永正17年(1520年)の勝沼氏討伐や、天文4年(1535年)の万力城攻めなど、数々の重要な合戦がこの館から指揮されました。組織的な軍事行動により国内の反抗勢力を制圧し、後の信玄による領土拡大の強固な基盤を築き上げたのです。
川中島の戦いと上杉謙信との攻防
信玄の時代、最大の軍事行動であった川中島の戦いにおいて、躑躅ヶ崎館は後方の最重要拠点として機能しました。天文22年(1553年)から永禄7年(1564年)にかけて5回にわたって繰り広げられた上杉謙信との死闘は、すべてこの館から出陣しています。
- 第一次(天文22年・1553年): 布施の戦い
- 第二次(弘治元年・1555年): 犀川の戦い
- 第三次(弘治3年・1557年): 上野原の戦い
- 第四次(永禄4年・1561年): 八幡原の戦い。信玄自らが出陣したし、「啄木鳥戦法」と謙信の「車懸りの陣」が激突した最大規模の激戦。
- 第五次(永禄7年・1564年): 塩崎の対陣
これらの戦いにおいて、館は兵の動員、補給物資の調達、負傷兵の治療など、後方支援の拠点として不可欠な役割を果たしました。
風林火山の軍略と情報戦略
信玄は孫子の兵法「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」を軍略の神髄としました。躑躅ヶ崎館はその戦略を練り上げる頭脳であり、各地に配置した間諜(スパイ)からの情報が集約される情報センターでもありました。敵の動向分析、同盟外交、経済戦略など、武力だけに頼らない総合的な戦争指導がこの地で行われたのです。
三方ヶ原の戦いと西上作戦
元亀3年(1572年)、信玄最後の大規模軍事行動となった西上作戦においても、躑躅ヶ崎館は司令部として機能しました。遠江・三河方面への進軍が指揮され、三方ヶ原で徳川家康軍を粉砕する大勝利を収めます。しかし、信玄の病状が悪化し、作戦は中断。翌天正元年(1573年)、信玄は信濃駒場伊那郡でその生涯を終えました。
見どころ – 遺構とミュージアムで知る戦国の息吹
国史跡としての価値と武田神社境内の遺構
昭和13年(1938年)に国史跡に指定された武田氏館跡は、戦国大名の居館の実態を知る上で極めて価値の高い遺跡です。武田神社となった現在も、境内には往時を偲ばせる遺構が良好な状態で保存されています。
- 堀と土塁: 神社を囲むように巡らされた堀跡と土塁は、館の規模と防御構造を今に伝えています。
- 古井戸: 「姫の井戸」や「武田水琴窟」など、当時から使われていたとされる井戸が点在し、今も清らかな水を湛えています。
- 曲輪の跡: 神社境内が館の中心部(主郭)にあたり、周辺には東曲輪、西曲輪といった区画の地名が残り、往時の広大な館の姿を想像させます。
- 発掘調査の成果: 平成時代から続く発掘調査により、主殿の建物跡や庭園の遺構、中国製の陶磁器や金箔瓦などが出土しています。これらの発見は、武田氏の権力と文化水準の高さを物語っています。
甲府市武田氏館跡歴史館(信玄ミュージアム)
武田神社に隣接するこの施設では、武田氏三代の歴史や館跡の発掘調査の成果を分かりやすく学ぶことができます。
- 常設展示室(無料): パネルや映像資料で武田氏の歴史と館の変遷を紹介。歴史に詳しくない方でも楽しめます。
- 特別展示室(有料): 発掘調査で出土した貴重な遺物を展示。より専門的な知識を得られます。
- 映像展示室: 若き日の信玄が登場し、往時の甲府の様子を臨場感豊かに紹介する映像コンテンツは必見です。
旧堀田古城園(国登録有形文化財)
信玄ミュージアムに隣接する「旧堀田古城園」は、昭和初期に建てられた近代和風建築群です。菱形の茶室など独特の意匠が見られ、歴史講座などに活用されています。近代甲府の歴史と文化を感じられる貴重なスポットです。
武田神社宝物殿
国指定重要文化財の太刀「銘 一(吉岡一文字作)」をはじめ、武田家ゆかりの甲冑、刀剣、信玄直筆とされる書状など、貴重な品々が収蔵・展示されています。信玄が愛用したと伝わる名刀は、戦国ファンならずとも一見の価値ありです。
アクセス – 旅の計画を万全に
武田氏館跡(武田神社)へのアクセスは、JR甲府駅が起点となります。
公共交通機関でのアクセス
- バス: JR甲府駅北口バスターミナルから、山梨交通バス「武田神社」行きまたは「積翠寺」行きに乗車(約8分)。「武田神社」バス停下車すぐ。日中は約15分間隔で運行。
- 徒歩: JR甲府駅北口から北へ約2.2km、徒歩約30分。甲府の街並みを楽しみながら歴史散策ができます。
自動車でのアクセス
- 高速道路: 中央自動車道「甲府昭和IC」からアルプス通り、武田通り経由で約8km(約20分)。
- 駐車場: 武田神社境内に無料駐車場あり。
- 台数: 普通車154台、大型バス10台
- 利用時間: 9:00~16:00
- ※観光シーズンや祭事の際は混雑が予想されるため、早めの到着をおすすめします。
施設利用案内
※料金や営業時間は変更される場合があるため、訪問前に公式サイトで最新情報をご確認ください。(以下は2025年9月時点の情報です)
- 武田神社:
- 境内拝観:自由
- 受付時間:8:30~17:00
- 宝物殿:
- 開館時間:9:30~16:00(最終受付 15:45)
- 休館日:毎週水曜日(祝日の場合は開館)、12月29日~31日
- 拝観料:大人・大学生 300円、高校生 200円、小・中学生 100円
- 信玄ミュージアム(甲府市武田氏館跡歴史館):
- 開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)
- 休館日:火曜日(祝日の場合は開館し、翌平日が休館)、年末年始
- 観覧料:特別展示室のみ有料(一般300円、高校生以下無料)
周辺観光 – 武田氏ゆかりの地を巡る
武田氏館跡とあわせて訪れたい、武田氏ゆかりの史跡をご紹介します。
要害山城 – 武田信玄生誕の地
館の北東約2kmに位置する詰城。武田信玄がこの城で生まれたと伝えられています。続日本100名城にも選定されており、山頂からは甲府盆地と武田氏館跡を一望できます。戦国時代の山城の雰囲気を体感できるハイキングコースが整備されています。
甲府城跡(舞鶴城公園)
武田氏滅亡後、豊臣秀吉の命で築かれた近世城郭。復元された稲荷櫓や壮大な石垣が見どころです。武田氏館跡から甲府城跡を巡ることで、戦国時代から江戸時代への甲府の歴史の移り変わりを感じることができます。
恵林寺 – 信玄公の菩提寺
武田信玄の墓所があることで知られる名刹。「心頭滅却すれば火もまた涼し」の言葉で有名な快川紹喜和尚の寺でもあります。夢窓疎石作庭と伝わる美しい庭園や、武田家ゆかりの宝物も必見です。
甲斐善光寺
川中島の戦いの際、信玄が信濃善光寺から本尊を移して創建した寺院。国宝に指定されている本堂と金堂は、東日本最大級の木造建築で、武田氏の権勢を物語っています。
新府城跡 – 武田勝頼最後の居城
勝頼が武田氏館から本拠を移した最後の城。完成からわずか3ヶ月で、武田氏滅亡とともに自らの手で火を放たれました。武田氏終焉の地として、栄華と悲劇の歴史を今に伝えています。
おすすめ周遊ルート(車利用・1日コース):
武田神社・信玄ミュージアム → 要害山城 → 甲斐善光寺 → 恵林寺
おわりに
武田氏館跡は、戦国大名・武田氏三代の栄光と挫折が刻まれた歴史の舞台です。信玄の「風林火山」に象徴される戦略が練られ、甲斐統一から天下を目指す壮大なドラマがここから始まりました。
現在の武田神社と信玄ミュージアムでは、最新の研究成果に基づき、戦国時代の息吹をリアルに感じることができます。甲府を訪れた際は、ぜひこの歴史深き地を訪れ、乱世を駆け抜けた武田氏の物語に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
▼主な参考文献
- 平山 優『武田信玄』(吉川弘文館、2006年)
- 平山 優『武田氏滅亡』(KADOKAWA/角川書店、2017年)
- 平山 優『長篠合戦と武田勝頼』(吉川弘文館、2014年)
- 丸島 和洋『武田勝頼』(平凡社、2017年)
- 丸島 和洋『武田信玄の家臣団』(中央公論新社、2015年)
- 柴辻 俊六『武田信玄―その生涯と領国経営』(新人物往来社、2009年)
- 柴辻 俊六『武田氏年表 信虎・信玄・勝頼』(高志書院、2010年)
- 秋山 敬『甲斐武田氏と国人―戦国大名成立過程の研究』(岩田書院、2003年)
- 笹本 正治『武田信玄―芳躅を後世に伝える』(ミネルヴァ書房、2005年)
- 山梨県教育委員会編『武田氏館跡:山梨県埋蔵文化財センター調査報告書』(山梨県教育委員会、2003年)
- 甲府市教育委員会『史跡武田氏館跡発掘調査報告書』(甲府市教育委員会、各年度版)
- 山梨県立博物館編『生誕500年記念特別展 武田信玄の生涯』(山梨県立博物館、2021年)
- 小和田 哲男『武田信玄と勝頼―最強軍団の光と影』(PHP研究所、2002年)
- 『山梨県史 通史編2 中世』(山梨県、2007年)
- 『甲府市史 通史編 第1巻 原始・古代・中世』(甲府市、1991年)








