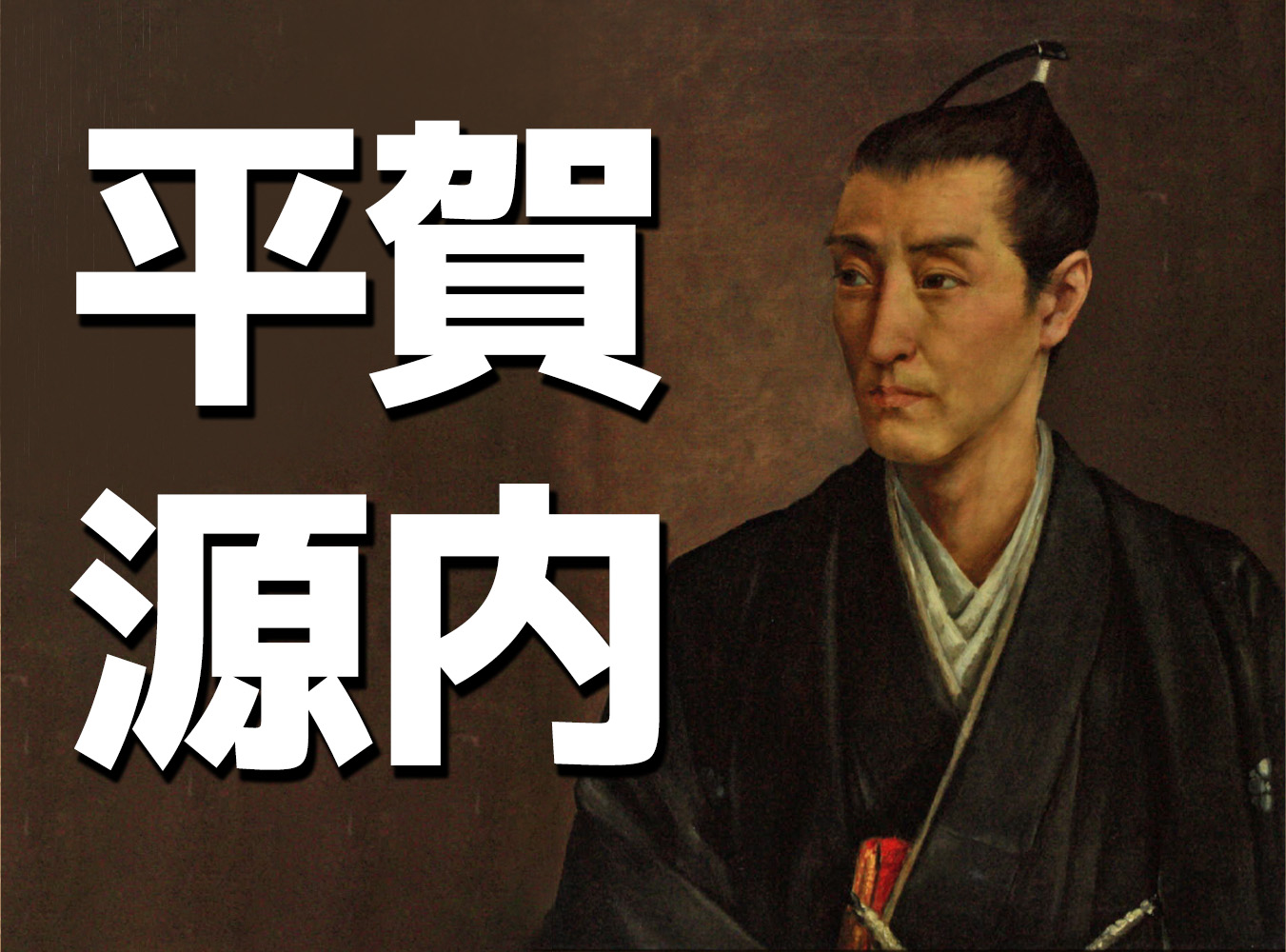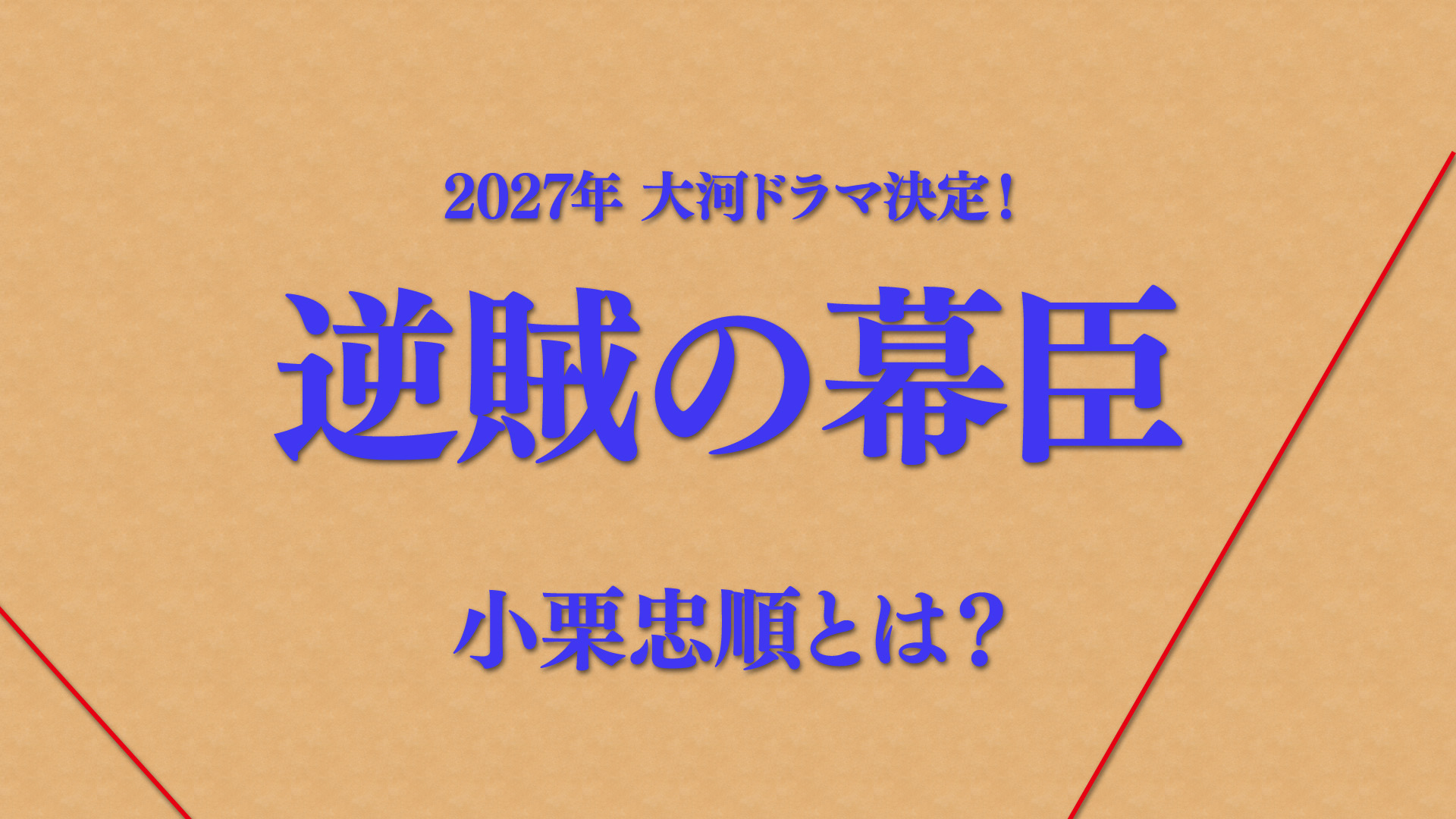- 戦国BANASHI TOP
- コラムの記事一覧
- 豊臣秀吉の出自の謎!百姓か、武士か?最新研究から解き明かす
豊臣秀吉の出自の謎!百姓か、武士か?最新研究から解き明かす
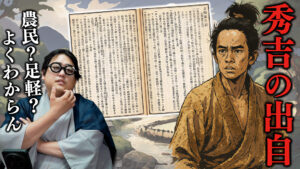
「鳴かぬなら鳴かせてみせようホトトギス」。裸一貫から身を起こし、天下人へと駆け上がった豊臣秀吉。その劇的な生涯は、多くの人々を魅了し続けています。一般的に秀吉は「尾張の貧しい百姓の子」として知られていますが、その出自には多くの謎が残されていることをご存知でしょうか。
「父は木下弥右衛門なのか、それとも筑阿弥という人物なのか?」「弟の秀長や妹の朝日は、本当に同じ父母から生まれたのか?」
これらの疑問は、江戸時代から議論が重ねられてきました。本記事では、信頼性の高い史料を基に、これらの謎を一つひとつ解き明かし、天下人・豊臣秀吉の「本当の出自」に迫ります。この記事を読めば、秀吉のサクセスストーリーの原点にある、彼の家の真の姿が浮かび上がってくるはずです。
目次
秀吉の父は誰か?「木下弥右衛門」説と「筑阿弥」説の対立
豊臣秀吉の父親については、当時の確かな史料がなく、江戸時代に成立した複数の書物によって異なる人物像が伝えられています。これが、秀吉の出自をめぐる議論の出発点となりました。
筑阿弥(竹阿弥)説:「太閤記」と「祖父物語」
秀吉の父について記す最も古い史料の一つが、小瀬甫庵が記した『太閤記』(1625年成立)です。これによると、秀吉の父は「筑阿弥(ちくあみ)」という人物で、尾張国愛知郡中村の住人であり、清須を拠点とする織田大和守家に仕えていたとされています。また、1642年に成立した『祖父物語』でも、父は「竹アミ」とされ、織田信長の同朋衆(主君の側に仕える芸人や茶人など)であったと記されています。
これらの史料は、秀吉の父を「筑阿弥」という出家姿の人物として描いています。
木下弥右衛門説:「太閤素生記」
一方、1676年以前に成立した土屋知貞の『太閤素生記』は、まったく異なる説を提示します。
- 実父: 木下弥右衛門という人物で、織田信長の父・信秀に仕える「鉄炮足軽」だった。[cite: 2][cite_start]弥右衛門は、秀吉が8歳の時(天文12年、1543年)に亡くなった。
- 継父: 弥右衛門の死後、母(のちの大政所・天瑞院殿)が再婚した相手が「竹阿弥(筑阿弥)」という信秀の同朋衆だった。
- 異父きょうだい: 筑阿弥と母の間には、弟の秀長と妹の朝日が生まれた。
この『太閤素生記』の記述により、「秀吉の実父は木下弥右衛門、継父が筑阿弥で、秀長や朝日は異父きょうだいである」という説が広く知られるようになりました。
実父と継父は別人か?それとも同一人物か?
秀吉の父をめぐる二つの説。これらは互いに矛盾しており、長らく研究者を悩ませてきました。しかし、近年の研究では、これらの史料を丹念に比較検討することで、新たな解釈が示されています。
「木下弥右衛門」という名の信頼性
『太閤素生記』が記す「木下弥右衛門」という名前ですが、この情報源は不明です。秀吉の姉・瑞竜院殿の菩提寺である瑞龍寺の記録にも、父の名は記されていません。
また、「鉄炮足軽」であったという記述も、歴史家の桑田忠親氏によって疑問が呈されています。天文12年(1543年)の段階で、織田信秀が組織的な「足軽の鉄砲隊」を保有していたとは考えにくいためです。
さらに、秀吉が後に名乗る「木下」という苗字は、妻・寧々の実家(本家)に由来するという説も、その実家である木下家定が秀吉から苗字を与えられているため、成り立ちません。
これらの点から、『太閤素生記』が記す「木下弥右衛門」という名前や「鉄炮足軽」といった記述の信頼性は低いと考えられます。
結論:父は「筑阿弥」という法号を持つ同一人物
では、「弥右衛門」と「筑阿弥」の関係はどう考えればよいのでしょうか。研究者は、この二人は別人ではなく、同一人物であった可能性が高いとみています。
『太閤素生記』の著者は、どこかで「弥右衛門」という父の通称(俗名)に関する情報を得たものの、法号である「筑阿弥」とは別の名前であるため、これを別人物と誤解して記述したのではないか、という推測です。
したがって、秀吉の父の実像は次のようにまとめることができます。
- 人物: 俗名は不明だが、「筑阿弥」という法号、そして死後は「妙雲院殿(みょううんいんでん)」という院号で呼ばれた人物。
- 仕官先: 『太閤記』が記すように、織田信秀・信長親子ではなく、尾張のもう一つの勢力であった清須織田大和守家に仕えていた可能性が高い。
- 死去年: 天文12年(1543年)に亡くなった。
これ以降、秀吉の父については、法号である「妙雲院殿」と記すのが最も適切と考えられます。
秀吉の家の階層は?「上層百姓」でありながら「没落」した一族
父の実像が見えてくると、次に気になるのは秀吉の家の社会的地位、すなわち「階層」です。単なる貧農だったのでしょうか、それとも別の顔を持っていたのでしょうか。
武家奉公する「上層百姓」
父・妙雲院殿は、清須織田家に武家奉公していました。これは、村に住みながら主君に仕える「在村被官」という立場であった可能性が高いと考えられます。
このような立場にある者は、村落内では比較的上層に位置していました。
その傍証となるのが、妙雲院殿の親戚関係です。
- 妹の一人: 青木重矩(あおき しげのり)に嫁ぎ、後の大名・青木重吉(しげよし)を産んだ。
- もう一人の妹(松雲院): 福島正信(ふくしま まさのぶ)に嫁ぎ、あの勇猛な武将・福島正則を産んだ。
[cite_start]
青木家や福島家のように、苗字を称する家と婚姻関係を結んでいること、そして妙雲院殿自身も妻(秀吉の母・天瑞院殿)を迎えていることから、彼の家が耕地などの相応の資産を持つ「上層百姓」であったことが強く示唆されます。江戸時代でも、結婚ができるのは納税の基盤となる耕地を持つ階層に限られていたからです。
父の代での「没落」と秀吉の貧しい少年時代
しかし、その一方で、秀吉の家が彼の少年時代に貧しかったこともまた事実です。[cite: 5][cite_start]秀吉自身が後年、北条氏直に宛てた手紙の中で「秀吉若輩の時、孤と成りて」と記しているように、父を早くに亡くし、苦しい生活を送っていました。
イエズス会の宣教師ルイス・フロイスの『日本史』にも「貧しい百姓の悴として生まれた」とあり、朝鮮の儒官・姜沆の『看羊録』には「父の家は元来貧賤で、農家に傭われてどうにかたつきをたてていた」と記録されています。
なぜ、相応の階層にあったはずの家が困窮したのでしょうか。理由は定かではありませんが、父・妙雲院殿が仕えていた清須織田家から何らかの理由で致仕(引退)せざるを得ない事態が起こり、没落したのかもしれません。そして父の死後、まだ少年であった秀吉には家を支えることができず、他家へ奉公に出るなど、流浪の生活を送ることになったと考えられます。
つまり、秀吉の出自は、単に「貧しい百姓」だったわけではなく、「かつては武家奉公する上層の百姓だったが、父の代に没落した家」と捉えるのが最も実態に近いと言えるでしょう。この没落によって、本来は持っていたはずの苗字も称せなくなったと考えられます。
秀吉の母と、きょうだいたちの真実
秀吉の人物像を形作った家族について、さらに詳しく見ていきましょう。
母・天瑞院殿(大政所)の実像
秀吉の母は、後に「大政所(おおまんどころ)」として絶大な権勢を誇った女性です。
- 生年: 永正14年(1517年)生まれ。[cite: 5][cite_start]秀吉を産んだのは21歳、夫の妙雲院殿が亡くなった時は27歳でした。
- 出自: 『太閤素生記』によれば、尾張国御器所村(名古屋市昭和区)の出身とされています。[cite: 2, 5][cite_start]父は関弥五郎兼員(せき やごろう かねかず)という、御器所村の有力百姓であったと考えられています。
- 名前: 通説では「なか」とされていますが、これは後世の所伝であり、当時の史料では確認できません。[cite: 5][cite_start]法号である「天瑞院殿(てんずいいんでん)」または「天瑞寺殿」と呼ぶのが適切です。
きょうだいは「同父同母」だった!
『太閤素生記』が記す「異父きょうだい説」は、秀吉の物語をよりドラマチックにしますが、これは事実だったのでしょうか。結論から言えば、秀吉、姉・瑞竜院殿、弟・秀長、妹・朝日の4人は、全員が同じ父(妙雲院殿)と母(天瑞院殿)から生まれた「同父同母」のきょうだいであった可能性が極めて高いです。
その最大の根拠は、彼らの生年と父の没年にあります。
- 父・妙雲院殿の没年: 天文12年(1543年)
- 弟・秀長の生年: 天文9年(1540年)
- 妹・朝日の生年: 天文12年(1543年)
弟の秀長も、妹の朝日も、父・妙雲院殿が亡くなる以前に生まれています。したがって、母が妙雲院殿の死後に筑阿弥と再婚して秀長と朝日を産んだ、とする『太閤素生記』の記述は、時系列的に成り立たないのです。このことから、高名な歴史家である桑田忠親氏も、早くから同父同母きょうだい説を唱えていました。
まとめ:秀吉の出自が教えてくれること
これまでの検証をまとめると、豊臣秀吉の出自は以下のような姿で浮かび上がってきます。
- 家系: 秀吉の家は、尾張国中村を拠点とし、清須織田家に仕える「在村被官」であった。[cite: 5][cite_start]村では相応の資産を持つ「上層百姓」の階層に属していた。
- 父: 筑阿弥(法号)または妙雲院殿(院号)と呼ばれる人物。[cite: 4][cite_start]天文12年(1543年)に死去。
- 母: 天瑞院殿(のちの大政所)。[cite: 5][cite_start]御器所村の有力百姓・関氏の娘。
- きょうだい: 姉の瑞竜院殿、弟の秀長、妹の朝日は、全員が同父同母のきょうだいである。
- 没落と貧困: 父の代に家が没落し、父の死後、少年時代の秀吉は孤児として貧しい生活を送った。
秀吉が「百姓から天下人へ」という、他に類を見ない出世を遂げたことは紛れもない事実です。しかし、その出発点は、単なる「無」ではありませんでした。彼の家には、かつて武家社会と繋がりを持ち、村の中で一定の地位を築いていたという「記憶」があったのです。
一度は没落し、どん底の生活を経験したからこそ、人々の心の機微を掴む術を身につけ、再び這い上がろうとする強烈なエネルギーが生まれたのかもしれません。上層階級の出自でありながら最下層の苦労を知るという、この稀有な経験こそが、後の天下人・豊臣秀吉を形作った最大の要因だったのではないでしょうか。
史料を丹念に読み解くことで、私たちは紋切り型の英雄像を超えた、より人間味あふれる秀吉の姿に触れることができるのです。
▼参考文献
羽柴秀吉一門 (シリーズ・織豊大名の研究)
https://amzn.to/4monVH6
羽柴秀吉とその一族 秀吉の出自から秀長の家族まで
https://amzn.to/3U2syul