- 戦国BANASHI TOP
- コラムの記事一覧
- 鬼柴田・柴田勝家とは?織田家筆頭家老の生涯と、豊臣秀吉との激闘の真相
鬼柴田・柴田勝家とは?織田家筆頭家老の生涯と、豊臣秀吉との激闘の真相
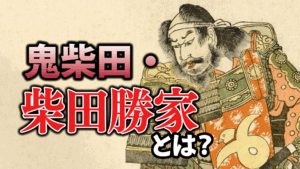
戦国時代、織田信長の天下統一事業を支えた勇将、柴田勝家(しばたかついえ)。その名は「鬼柴田」や「かかれ柴田」といった勇猛果敢な異名と共に、今も歴史ファンの心を捉えてやみません。
しかし、その一方で、本能寺の変後、羽柴秀吉(豊臣秀吉)との覇権争いに敗れ、悲劇的な最期を遂げた武将としても知られています。
この記事では、織田家筆頭家老として活躍した柴田勝家の生涯を紐解きながら、彼の実像、豊臣秀吉やその弟・秀長との関係、そして歴史における重要性に迫ります。近年、再評価が進む勝家の魅力を、歴史ファンの方々に向けて分かりやすく解説します。
目次
柴田勝家の出自と織田信長への帰参
柴田勝家は、大永2年(1522年)頃、尾張国(現在の愛知県西部)に生まれたとされていますが、その出自については諸説あります。一説には、足利氏の一門である斯波(しば)氏の流れをくむとも言われています。
当初、勝家は織田信長の父・信秀に仕え、その死後は信長の弟・織田信行(のぶゆき、信勝とも)に家老として仕えました。当時、奇抜な言動から「うつけ者」と評された信長に対し、品行方正とされた信行を後継者に推す動きがあり、勝家もこれに加担します。
弘治2年(1556年)、信行方は信長に対し兵を挙げますが、「稲生の戦い」で敗北。勝家は一度は信長に敵対したものの、その武勇を惜しまれ、母・土田御前の嘆願もあって許され、信長に忠誠を誓うことになります。
さらに、弘治4年(1558年)には、信行が再び謀反を企てていることを信長に密告。これにより信行は粛清され、勝家は信長の信頼を得て、織田家家臣団の中核を担う存在となっていきました。
この経緯は、勝家が単なる猛将ではなく、時勢を読む冷静な判断力も持ち合わせていたことを示唆しているかもしれません。
織田家筆頭家老への道―数々の武功と「鬼柴田」の勇名
信長に仕えた勝家は、その期待に応えるように各地の戦で目覚ましい武功を挙げていきます。「かかれ柴田」の異名は、常に先陣を切って勇猛果敢に戦う姿から名付けられたと言われています。
主な戦功としては、六角氏との戦いや、元亀元年(1570年)の「姉川の戦い」での活躍が挙げられます。
また、石山本願寺との長年にわたる戦い(石山合戦)や、伊勢長島一向一揆の鎮圧など、織田軍の主要な戦いの多くに参戦し、その武名を轟かせました。
元亀元年(1570年)の長光寺城(滋賀県近江八幡市)の戦いでは、六角義賢軍に包囲され、水の手を断たれるという絶体絶命の危機に陥ります。
この時、勝家は残された水瓶を将兵の前で打ち割り、「渇して死するより、討って死すべし」と兵を鼓舞し、決死の突撃を敢行して勝利を収めたという逸話が残っています
。これが世に名高い「瓶割り柴田(かめわりしばた)」の由来であり、彼の勇猛さと機転を示すエピソードとして語り継がれています。
こうした数々の戦功により、勝家は織田家中でその地位を高め、天正3年(1575年)には、越前国(えちぜんのくに、現在の福井県東部)を与えられ、北陸方面軍の総司令官に任命されます。これは、織田家における彼の重要性が一段と高まり、後の筆頭家老へと繋がる大きな一歩と言えるでしょう。
北陸方面軍総司令官としての活躍と越前統治
北陸方面軍総司令官となった勝家は、長年織田軍を苦しめた越前一向一揆の鎮圧に成功します。その後の越前統治では、武将としてだけでなく、優れた為政者としての一面も見せました。
勝家は、越前の本拠地として北ノ庄城(きたのしょうじょう、現在の福井市)を築城。この城は九層の天守閣を持つ壮大なものであったと伝えられ、織田信長の安土城にも匹敵する規模だったと言われています。城下町の整備にも力を入れ、荒廃した越前の復興に努めました。
政策面では、豊臣秀吉よりも早く「刀狩り(かたながり)」や「検地(けんち)」を実施したとされています。
特に、天正4年(1576年)に村ごとに年貢額を申告させた「指出検地(さしだしけんち)」は、江戸時代の石高制の先駆けとも言える先進的なものでした。
また、治安維持のための「北庄法度(きたのしょうはっと)」を発令し、農村復興のための掟書を公布するなど、領国経営にも手腕を発揮しました。
宣教師ルイス・フロイスも、その権勢と活躍ぶりを「織田信長のようだ」と評したと伝えられています。
しかし、北陸は依然として上杉謙信という強大な敵と対峙する最前線でした。
天正5年(1577年)の「手取川の戦い」では、勝家率いる織田軍は上杉謙信に敗北を喫します。
この敗戦は、勝家にとって大きな痛手となりましたが、翌年に謙信が急死したことで、織田軍は北陸での勢いを盛り返すことになります。
本能寺の変と清洲会議―秀吉との対立激化
天正10年(1582年)6月2日、本能寺の変が勃発し、主君・織田信長が明智光秀に討たれます。
当時、勝家は越中で上杉軍の魚津城を攻略中であり、信長の死を知ったのは数日後のことでした。すぐに京へ向かおうとしますが、上杉軍の反撃に遭い、迅速な行動が取れませんでした。
その間、備中高松城(びっちゅうたかまつじょう、現在の岡山市)で毛利氏と対陣していた羽柴秀吉は、驚異的な速さで京へ戻り(「中国大返し」)、山崎の戦いで明智光秀を討ち破ります。これにより、秀吉は織田家中で一気に発言力を増しました。
信長の後継者と遺領の配分を決定するために開かれた「清洲会議(きよすかいぎ)」で、柴田勝家と羽柴秀吉の対立は決定的となります。
勝家は信長の三男・織田信孝(のぶたか)を後継者に推しましたが、秀吉は信長の嫡孫(ちゃくそん、正当な跡継ぎとなる孫)・三法師(さんぽうし、後の織田秀信)を擁立。会議の結果、丹羽長秀(にわながひで)や池田恒興(いけだつねおき)らが秀吉案に賛同し、三法師が後継者となることが決定します。
この会議で、勝家は長年の願いであった信長の妹・お市の方(おいちのかた)との結婚を果たします。
お市の方は浅井長政(あざいながまさ)に嫁いでいましたが、長政の死後は織田家に戻っていました。
この結婚は、勝家にとって織田家内での立場を強化する意味合いがあったと同時に、織田家の血筋を守りたいという思いがあったのかもしれません。
清洲会議後、勝家と秀吉の権力闘争はますます激化。勝家は滝川一益(たきがわかずます)や織田信孝と結び、秀吉包囲網を形成しようとします。
一方の秀吉も巧みな調略で味方を増やし、両者の対決は避けられない状況となっていきました。
賤ヶ岳の戦い―勇将、北ノ庄に散る
天正11年(1583年)、柴田勝家と羽柴秀吉はついに「賤ヶ岳の戦い(しずがたけのたたかい)」で激突します。当初は一進一退の攻防が続きましたが、戦況は徐々に秀吉方に有利に傾いていきます。
この戦いにおける勝家の敗因については、いくつかの要因が指摘されています。
佐久間盛政(さくまもりまさ)の突出
勝家の甥である佐久間盛政は、秀吉本隊が美濃(みの、現在の岐阜県南部)に出陣した隙を突いて敵陣深くに攻め込みますが、秀吉の迅速な反転(「美濃大返し」)により孤立し、大きな損害を出しました。
前田利家(まえだとしいえ)の戦線離脱
勝家の与力(よりき、配下の武将)であった前田利家が、戦闘の最中に突如戦線を離脱。利家は秀吉とも旧知の仲であり、この離脱は柴田軍の士気を大きく低下させました。利家の離脱の背景には、秀吉による調略があったとも、前田家の将来を案じた末の苦渋の決断だったとも言われています。歴史書『甫庵太閤記(ほあんたいこうき)』では、この利家の離脱が隠蔽され、佐久間盛政の行動が敗因として強調されたという説もあります。
秀吉の巧みな戦略
秀吉は情報収集や調略を駆使し、勝家方の結束を乱しました。また、兵站(へいたん、物資補給)や兵の移動も迅速で、戦局を有利に進めました。
賤ヶ岳で敗れた勝家は、居城・北ノ庄城へ敗走。追撃する秀吉軍に包囲される中、もはやこれまでと悟った勝家は、妻・お市の方と共に自害を選びます。時に勝家62歳、お市の方37歳であったと伝えられています。
お市の方は、娘である浅井三姉妹(茶々、初、江)を城から逃がした後、勝家と最期を共にしました。この時、勝家は長年仕えた家臣たちに城を去るよう諭したとされ、その度量の広さを示す逸話として残っています。
柴田勝家と豊臣秀吉の弟・豊臣秀長(とよとみひでなが)との直接的な関係を示す史料は多くありません。
しかし、秀長は秀吉の片腕として数々の戦に従軍しており、賤ヶ岳の戦いにも秀吉軍の主要武将として参陣していたと考えられています。
秀長の冷静な戦況分析や補佐が、秀吉の勝利に貢献したことは想像に難くありません。勝家にとって、秀吉だけでなく、秀長もまた手ごわい相手だったことでしょう。
柴田勝家の歴史的評価と人物像
柴田勝家は、その勇猛さから「鬼柴田」と恐れられた一方で、配下からの信頼も厚く、統治能力にも長けた武将でした。信長への忠誠心は非常に強く、その古い武士道を貫いた生き様は、多くの歴史ファンの心を打ちます。
従来、勝家は秀吉の引き立て役として語られることが多かったかもしれません。
しかし、近年の研究では、織田家筆頭家老としての実力や、信長亡き後の天下を争う上で秀吉にとって最大のライバルであったという評価が高まっています。
もし賤ヶ岳の戦いで勝家が勝利していれば、その後の歴史は大きく変わっていた可能性も否定できません。
彼の最期にまつわる逸話として、北ノ庄城落城後、勝家の亡霊が首のない馬に乗って現れるという伝説が福井の地に残されています。これは、彼の無念の死を人々が悼み、語り継いだものかもしれません。
柴田勝家は、戦国という激動の時代を駆け抜けた、まさに「もののふ」と呼ぶにふさわしい武将でした。その生涯は、現代の私たちにも多くのことを教えてくれます。
まとめ
柴田勝家は、織田信長の下で数々の武功を立て、織田家筆頭家老として重きをなした名将です。
勇猛果敢なだけでなく、優れた統治能力も持ち合わせていました。本能寺の変後、豊臣秀吉との覇権争いに敗れ、賤ヶ岳の戦いで悲劇的な最期を遂げましたが、その忠義心と武士としての生き様は、今もなお多くの人々を魅了し続けています。
彼の生涯を通じて、戦国時代の武将たちの生き様や、歴史の大きな転換点を感じていただければ幸いです。








