- 戦国BANASHI TOP
- コラムの記事一覧
- 【島津義久】秀吉に屈した薩摩の巨人~その生涯と九州統一の夢、豊臣政権との駆け引き~
【島津義久】秀吉に屈した薩摩の巨人~その生涯と九州統一の夢、豊臣政権との駆け引き~
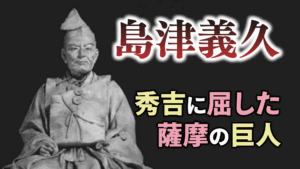
戦国時代の九州を席巻し、一時はその大部分を手中におさめた島津義久(しまづ よしひさ)。
「三州(さんしゅう)の総大将」と称され、弟たちと共に島津家の勢力を飛躍的に拡大させましたが、天下統一を目指す豊臣秀吉の前に屈し、臣従(しんじゅう)の道を歩むことになります。
本記事では、島津義久の波乱に満ちた生涯と、彼が九州の覇者(はしゃ)となるまでの道のり、そして豊臣兄弟との複雑な関係を中心に、歴史ファンに向けて分かりやすく解説します。
義久とは一体どのような人物だったのか?
彼の強さの秘密、そして天下人・秀吉とどのように渡り合ったのか。
その知られざる魅力に迫ります。
目次
島津義久の誕生と家督相続~英傑の片鱗~
島津義久は、天文2年(1533年)、島津貴久(たかひさ)の長男として薩摩国(さつまのくに、現在の鹿児島県西部)で生まれました。
幼名は虎寿丸(とらじゅまる)。
島津家は鎌倉時代から続く名門ですが、義久が生まれた頃は分家や国人(こくじん、在地勢力)の台頭により、その勢力は盤石とは言えませんでした。
父・貴久は、島津家内部の抗争を制し、薩摩・大隅(おおすみ)・日向(ひゅうが)の三州統一を目指します。
義久は、父の背中を見ながら成長し、その才覚を徐々に現していきます。
特に、祖父である島津忠良(ただよし)は、義久を「三州の総大将としての材徳を備えている」と高く評価したと言われています。
永禄9年(1566年)、義久は34歳で家督を継ぎ、名実ともに島津家の当主となります。
ここから、島津家の本格的な九州統一への道が始まります。
弟の義弘(よしひろ)、歳久(としひさ)、家久(いえひさ)という優秀な弟たちと共に、破竹の勢いで領土を拡大していくのです。
九州統一への道~三州統一から沖田畷の戦いまで~
家督を継いだ義久は、父の悲願であった三州統一を最優先課題とします。
弟たちとの巧みな連携プレーは、まさに「島津四兄弟」の真骨頂でした。
長男の義久が全体を統括し、次男の義弘が軍事指揮、三男の歳久が知略、四男の家久が突撃隊長といった役割分担があったとも言われています。
もちろん、これは後世のイメージも含まれますが、兄弟がそれぞれの持ち味を活かして協力したことは間違いありません。
木崎原(きざきばる)の戦いと耳川(みみかわ)の戦い
元亀3年(1572年)の木崎原の戦いでは、伊東氏の大軍を寡兵(かへい、少数の兵)で破り、日向における島津氏の優位を確立します。
そして、天正6年(1578年)の耳川の戦い。
これは、九州の歴史を語る上で欠かせない重要な合戦です。
キリシタン大名として知られる大友宗麟(おおとも そうりん)率いる大軍と激突。
島津軍は、得意の「釣り野伏せ(つりのぶせ)」という戦術を用い、大友軍を壊滅状態に追い込みました。
釣り野伏せとは、中央の部隊がわざと負けたように見せかけて後退し、追撃してきた敵を左右に伏せていた部隊で包囲殲滅(せんめつ)するという高度な戦術です。
この勝利により、大友氏は大きく勢力を後退させ、島津家は三州統一をほぼ成し遂げます。
沖田畷(おきたなわて)の戦い~龍造寺氏を破り九州二強へ~
三州を固めた島津家の次の標的は、肥前(ひぜん、現在の佐賀県・長崎県)の龍造寺隆信(りゅうぞうじ たかのぶ)でした。
龍造寺隆信は、「肥前の熊」と恐れられた勇猛な戦国大名です。
天正12年(1584年)、両者は島原半島(しまばらはんとう)の沖田畷(おきたなわて)で激突します。
この戦いでも島津軍は巧みな戦術を見せ、龍造寺隆信を討ち取り、龍造寺氏の勢力を大幅に削ぐことに成功しました。
これにより、九州は島津氏と、辛うじて勢力を保つ大友氏の二強時代へと突入します。
島津義久の九州統一は、もはや時間の問題かと思われました。
この頃の義久の勢いは凄まじく、大友宗麟は中央の豊臣秀吉に助けを求めます。
これが、後の九州平定へと繋がっていくのです。
豊臣秀吉の九州平定~巨龍、墜つ~
天下統一を進める豊臣秀吉にとって、九州の島津氏の台頭は看過できないものでした。
天正13年(1585年)、関白となった秀吉は、全国の大名に私戦を禁じる「惣無事令惣無事(そうぶじれい)」を発します。
これは、大名間の私的な戦闘を禁じる命令で、従わない場合は武力で制圧するという最後通告のようなものでした。
補足:惣無事令は藤木久志氏がドイツの帝国平和令などを参考に、秀吉が全国的に発布した法令と言われているが、原本が確認できず、藤井譲治氏などの研究により全国的な法令ではないと言われています。
しかし、九州の覇権を目前にしていた島津義久は、この命令をすぐには受け入れませんでした。
これに対し、秀吉は弟の豊臣秀長(とよとみ ひでなが)を総大将とする大軍を九州へ派遣。
さらに、自らも九州へ出陣する構えを見せます。
戸次川(へつぎがわ)の戦いと根白坂(ねじろざか)の戦い
豊臣軍の先鋒(せんぽう)と島津軍は、豊後(ぶんご、現在の大分県)の戸次川で激突(戸次川の戦い)。
この戦いでは、島津家久の活躍により、長宗我部元親の嫡男・信親(のぶちか)や十河存保(そごう まさやす)といった四国勢の勇将たちが討死するという大波乱が起こります。
豊臣軍は大きな損害を受けましたが、これは圧倒的な物量で迫る豊臣軍のほんの一角に過ぎませんでした。
秀吉本隊が九州に上陸すると、島津方は各地で敗退。
天正15年(1587年)、日向の根白坂の戦いで島津軍は豊臣軍に決定的な敗北を喫します。
この敗戦を受け、ついに島津義久は降伏を決意。
泰平寺(たいへいじ、現在の鹿児島県薩摩川内市)で秀吉と会見し、臣従を誓いました。
一時は九州のほぼ全土を手中に収めた義久の九州統一の夢は、ここに潰えることとなります。
降伏の条件として、島津氏の領地は薩摩・大隅の二国と日向の一部に削減されましたが、それでも大大名としての地位は保たれました。
これは、秀吉が島津氏の力を完全に削ぐよりも、巧みに取り込むことを選んだ結果と言えるでしょう。
また、秀吉の弟・秀長が、島津家との交渉において穏健な姿勢で臨んだことも、島津家の本領安堵(ほんどあんど、領地の保障)に繋がったという説もあります。
秀長は、九州平定の実質的な司令官であり、島津家に対して「国々法度書付(くにぐにほうどしょつけ)」と呼ばれる文書を発給するなど、戦後処理にも深く関わったと考えられています。
臣従後の義久~したたかな「田舎者」~
秀吉に臣従した後、義久は弟の義弘に家督を譲ったとされていますが、実権は依然として義久が握り続けていたと言われています。
これは「両殿体制(りょうどたいせい)」とも呼ばれ、義久が内政や外交を、義弘が軍事や中央との折衝を担当するという役割分担があったようです。
義久は、豊臣政権下で中央の政治とは距離を置き、薩摩での領国経営に専念します。
検地(けんち、田畑の面積や収穫量を調査すること)や刀狩(武士以外の身分に武器の所持を認めさせないこと)を拒否したり、朝鮮出兵への兵力供出を渋ったりするなど、中央政権の意向に簡単には従わない「したたかさ」を見せました。
一見すると反抗的にも見えますが、これは島津家の独立性を保ち、領民の負担を軽減しようとする義久なりの戦略だったのかもしれません。
秀吉は、義久を「田舎者で、何も分かっていない」と評したとも伝えられていますが、その実、義久の老獪(ろうかい)な政治手腕に手を焼いていたのではないでしょうか。
文化人としての一面もあり、京都の公家(くげ)である近衛前久(このえ さきひさ)や、連歌師(れんがし)の里村紹巴(さとむら じょうは)らとも交流がありました。
秀吉との茶会に参加した記録も残っており、単なる武辺者(ぶへんもの、武勇に優れただけの人物)ではなかったことがうかがえます。
関ヶ原の戦いと島津の退き口~義久の決断~
慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発します。
この時、島津義弘は西軍に与(くみ)して参戦しますが、義久は本国・薩摩から動きませんでした。
義弘への援軍も送らなかったため、兄弟間の不和を疑う声もあります。
しかし、これは東西どちらが勝利しても島津家が生き残れるようにという、義久の深謀遠慮(しんぼうえんりょ)だったという説が有力です。
結果として西軍は敗北。
義弘は、敵中突破という壮絶な「島津の退き口(のきくち)」を敢行し、薩摩へ生還します。
戦後、徳川家康は島津氏の責任を追及しようとしますが、義久は巧みな外交交渉を展開。
最終的には本領安堵を勝ち取り、島津家は改易(かいえき、領地没収)の危機を乗り越えました。
この粘り強い交渉は、義久の政治家としての真骨頂と言えるでしょう。
近年の研究では、義久と義弘は必ずしも一枚岩ではなく、豊臣政権への向き合い方などで意見の対立があったとも指摘されています。
義久は中央政権の介入を極力嫌い、一方の義弘は中央との協調によって家名を保とうとした、という見方です。
この緊張関係が、関ヶ原の戦いにおける複雑な対応に繋がったのかもしれません。
晩年と死~薩摩藩の礎を築く~
関ヶ原の戦い後、義久は領国経営にさらに力を注ぎます。
琉球(りゅうきゅう、現在の沖縄県)への侵攻(慶長14年、1609年)も、義久の指示のもとで行われました。
これは、江戸幕府の許可を得て行われたもので、薩摩藩の財政を潤す大きな要因となりました。
慶長16年(1611年)、島津義久は国分(こくぶ、現在の鹿児島県霧島市)の舞鶴城(まいづるじょう)でその生涯を閉じました。
享年79(満77歳没)。
九州統一の夢は道半ばで潰えましたが、その巧みな統治と外交術により、島津家を近世大名として存続させ、後の薩摩藩の礎(いしずえ)を築いた功績は非常に大きいと言えます。
義久の統治スタイルについては、重臣たちの合議を重視しつつも、最終的な決定はクジや神慮(しんりょ、神のお告げ)といった神秘的な要素も利用して巧みに誘導した、という研究もあります。
これは、強大な力を持つ家臣団をまとめるための、義久ならではの知恵だったのかもしれません。
また、タバコ栽培を奨励し、藩の財源としたという逸話も残っています。
島津義久の評価~現代に語り継がれるもの~
島津義久は、弟の島津義弘の武勇伝が華々しいため、その影に隠れがちな存在でした。
しかし、近年の研究では、その卓越した政治手腕や、大局を見据えた判断力が再評価されています。
九州の大部分を制圧した軍事指導者としての側面と、豊臣・徳川という巨大権力と渡り合い家名を保った政治家としての側面を併せ持つ、稀有(けう)な武将だったと言えるでしょう。
彼の生涯は、地方の雄(ゆう)が中央の巨大権力とどのように向き合い、生き残りを図ったのかという、戦国時代の一つの典型を示しています。
また、兄弟の力を結束させて勢力を拡大したリーダーシップは、現代の組織運営にも通じるものがあるかもしれません。
鹿児島県歴史資料センター黎明館(れいめいかん)には、島津義久の肖像画や羽織が所蔵されている可能性があり、彼の姿を偲(しの)ぶことができます(※閲覧や画像利用には確認が必要です)。
島津義久という人物を通じて、戦国時代の九州のダイナミズムと、そこに生きた人々の知恵や葛藤を感じていただければ幸いです。








