- 戦国BANASHI TOP
- コラムの記事一覧
- 豊臣秀吉の姉「とも(日秀尼)」悲劇を乗り越え祈りに生きた92年の生涯
豊臣秀吉の姉「とも(日秀尼)」悲劇を乗り越え祈りに生きた92年の生涯
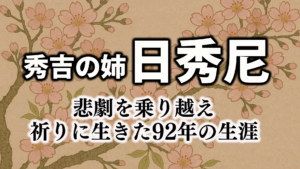
豊臣秀吉といえば、農民の身分から戦国時代を駆け上がり天下統一を成し遂げた稀代の英雄です。彼を支えた女性として、妻の「ねね(北政所、きたのまんどころ)」や母の「なか(大政所、おおまんどころ)」が有名ですが、実は秀吉にはもう一人、彼の栄光と、そして一族の悲劇を間近で見つめ続けた実の姉がいたことをご存知でしょうか。その名は「とも」、出家して「日秀尼(にっしゅうに)」と名乗った女性です。彼女の生涯は、豊臣家の興亡と深く結びつき、息子たちの栄達と悲劇的な運命に翻弄されながらも、最後は深い信仰に生きた、まさに波乱万丈なものでした。この記事では、あまり語られることのない日秀尼の92年間の生涯と、彼女が生きた時代の意味を紐解いていきます。
目次
とも(日秀尼)とは? その生涯と豊臣家における役割
まずは、日秀尼がどのような人物だったのか、その基本的な情報から見ていきましょう。
生い立ちと家族構成
ともは、天文3年(1534年)(天文元年(1532年)生まれとする異説もあり)尾張国(現在の愛知県西部)で、父・木下弥右衛門(きのした やえもん)と母・大政所の間に生まれました。豊臣秀吉の実姉にあたります。弟には、秀吉の片腕として活躍した豊臣秀長、妹には徳川家康に嫁いだ朝日姫がいますが、この二人は父が異なるため(大政所の再婚相手、竹阿弥(ちくあみ))、異父弟妹となります。
彼女は後に、弥助(やすけ)という男性に嫁ぎ、夫は後に三好吉房(みよし よしふさ)と名乗りました。この弥助も、秀吉の出世に伴い武士としての地位を得ていくことになります。
ともと吉房の間には、三人の息子が生まれました。長男が豊臣秀次(羽柴秀次)、次男が豊臣秀勝(羽柴秀勝)、三男が豊臣秀保(羽柴秀保)です。彼らは、叔父である秀吉や秀長の養子となり、豊臣政権の中核を担う重要な存在となっていきます。
弟・秀吉の天下統一と、ともの息子たち
秀吉が織田信長のもとで頭角を現し、本能寺の変後は天下統一へと突き進む中で、彼の親族もまた重要な役割を担うようになります。血縁を重視した秀吉にとって、姉の子である甥たちは、信頼できる身内として重用されました。
長男の秀次は、叔父である秀吉に実子がいなかった(あるいは幼くして亡くなった)ため、早くから後継者候補として期待され、秀吉の養子となります。そして、秀吉が天下を統一し関白の位に就くと、秀次は秀吉に次ぐ関白の座を譲り受けることになります。これは、ともにとって、そして一族にとって最大の栄誉と言える出来事でした。
次男の秀勝も秀吉の養子となり、各地の戦で功績を挙げますが、残念ながら文禄の役(朝鮮出兵)の最中に24歳という若さで病死してしまいます。三男の秀保は、大和郡山城主であった豊臣秀長の養子となり、秀長の死後その所領を継ぎますが、彼もまた17歳という若さで病に倒れてしまいました。
息子たちが次々と豊臣政権の重職に就くことは、母であるともにとって誇らしいことであったでしょう。しかし、その栄光の陰には、常に政争の不安や、息子たちの身を案じる母としての苦悩もつきまとっていたのかもしれません。
悲劇の関白・豊臣秀次事件と母・日秀尼の苦悩
ともの人生において、最大の悲劇であり転機となったのが、長男・秀次を襲った「豊臣秀次事件」です。
秀頼の誕生と狂い始めた運命の歯車
秀吉から関白職を譲られ、聚楽第で政務を執っていた秀次。しかし、秀吉に実子・豊臣秀頼が誕生すると、状況は一変します。我が子の可愛さからか、秀吉は次第に秀次に対して猜疑心を抱くようになります。「秀次が謀反を企んでいる」という噂も流れ始め、二人の関係は急速に悪化していきました。
この背景には、秀吉の老いと、秀頼への溺愛、そして豊臣政権内部の権力闘争など、様々な要因が複雑に絡み合っていたと考えられています。
秀次切腹と一族処刑の悲劇
文禄4年(1595年)夏、ついに秀次は謀反の疑いをかけられ、高野山へ追放、そして切腹を命じられてしまいます。秀次は潔く自刃しましたが、悲劇はそれだけでは終わりませんでした。秀吉は、秀次の妻子や側室、侍女に至るまで、39名もの女性や子供たちを京都の三条河原で処刑するという、あまりにも残忍な命令を下したのです。
この時、処刑される人々の中には、ともの孫にあたる秀次の幼い子供たちも含まれていました。わが子である秀次を失い、さらに多くの孫たちまでも無残に殺されてしまうという現実は、母として、祖母としてのともにとって、筆舌に尽くしがたい衝撃と悲しみをもたらしたことでしょう。
この事件に連座し、ともの夫である三好吉房も讃岐国(現在の香川県)へ配流となってしまいました。
母としての悲しみと絶望
次男・秀勝は既に病死しており、三男・秀保もこの事件の直前に亡くなっていた(一説には秀吉による暗殺説も囁かれますが定かではありません)とも言われています。そして、最も頼りにしていた長男・秀次とその家族の無残な死。相次ぐ不幸は、ともを深い悲しみの淵へと突き落としました。この悲劇こそが、彼女の後半生を大きく方向づけることになったのです。
出家、そして祈りの日々へ – 日秀尼の後半生
愛する息子たち、そして多くの孫たちを失ったともは、深い絶望の中で一つの決断をします。それは、仏の道に入ることで、亡き者たちの菩提を弔い、その魂の救済を祈るという生き方でした。
悲しみを乗り越えて仏門へ
秀次事件の翌年、慶長元年(1596年)、ともは京都の日蓮宗本山である本圀寺(ほんこくじ)の空竟院日禎(くうきょういんにっしん)上人のもとで出家し、「日秀(にっしゅう)」という法名を授かります。時に、彼女は60歳を超えていました。ここから、彼女の「日秀尼」としての後半生が始まります。
善正寺(ぜんしょうじ)の創建
日秀尼はまず、秀次とその妻子、そして非業の死を遂げた一族の霊を慰めるため、京都の嵯峨(さが)の地に善正寺(ぜんしょうじ)という寺を建立しました。この寺は、秀次の菩提寺として、また日秀尼自身の深い祈りの場となったのです。善正寺には、日秀尼の肖像画や木像が伝えられており、彼女の面影を今に伝えています。
皇室ゆかりの尼門跡寺院・瑞龍寺(村雲御所)の建立
さらに日秀尼は、亡き秀次の冥福を祈るため、より大きな寺院の建立を発願します。彼女の深い信仰心と、そして豊臣家の縁故もあってか、この願いは朝廷にも届きました。時の後陽成天皇は、日秀尼の願いを嘉納し、寺地と寺号「瑞龍寺(ずいりゅうじ)」を賜ります。この瑞龍寺は京都の村雲(むらくも)の地に建てられ、皇女や高位の貴族の娘が入寺する「尼門跡寺院(あまもんぜきじいん)」という極めて格式の高い寺院となりました。「村雲御所(むらくもごしょ)」とも呼ばれ、その後の日本の仏教文化、特に女性の仏教信仰において重要な役割を果たすことになります。
秀吉の死後、豊臣家の力は急速に衰えていきますが、日秀尼が建立した瑞龍寺は、皇室との深いつながりによってその法灯を守り続けました。これは、日秀尼の深い信仰心と、彼女の持つ人徳、そして時代の大きな流れの中で、一つの救いを見出そうとした彼女の強い意志の表れと言えるでしょう。瑞龍寺は後に、秀次の居城であった近江八幡(おうみはちまん)の八幡山城跡に移転し、現在もその歴史を伝えています。
豊臣家の終焉を見届けた長寿の尼
日秀尼は、戦国時代の終わりから江戸時代初期という、まさに日本史の大きな転換期を生きました。そして、弟・秀吉が築き上げた豊臣家の栄華とその後の没落を、誰よりも間近で見つめ続けることになります。
秀吉の死、そして関ヶ原、大坂の陣
慶長3年(1598年)、弟であり天下人であった豊臣秀吉が波乱の生涯を閉じます。その後、豊臣政権は徳川家康と石田三成率いる大老達との間で急速に内部対立を深め、慶長5年(1600年)には徳川家康率いる東軍と、秀吉の意思を継いだ石田三成率いる西軍が衝突した関ヶ原の戦いが勃発。この戦いで西軍が敗れたことにより、豊臣家の影響力は大きく削がれてしまいます。
そして、慶長19年(1614年)からの大坂の陣(冬の陣・夏の陣)で豊臣家は徳川家康に滅ぼされ、秀吉の血筋は(表向きには)途絶えてしまいました。日秀尼は、これらの出来事をどのような思いで見つめていたのでしょうか。自身が深く関わった豊臣家が、まるで砂の城のように崩れ去っていく様を目の当たりにするのは、計り知れない苦痛であったに違いありません。
最後の孫との関わり – 真田幸村の娘・御田姫の保護
豊臣家滅亡後、日秀尼に関する興味深いエピソードが伝えられています。それは、大坂夏の陣で討死した真田幸村(信繁)の娘であり、かつて処刑された秀次の孫娘(秀次の娘・隆清院が幸村の妻となっていた)にあたる御田姫(おたひめ)を、日秀尼が保護したというものです。
徳川方の厳しい追及を逃れ、日秀尼のもとに身を寄せた御田姫。日秀尼は、かつて秀吉によって奪われた孫たちの命を想い、この幼い曾孫を慈しんだのかもしれません。この逸話は、日秀尼の深い母性愛と、豊臣の血を絶やしたくないという密かな願い、あるいは単に戦乱の犠牲者への純粋な慈悲心からきた行動なのか、歴史のロマンを感じさせます。
静かな最期
豊臣家の栄華も没落も、そして新たな徳川の世の始まりも見届けた日秀尼は、寛永2年(1625年)4月24日、京都でその波乱に満ちた生涯を閉じました。享年92歳。当時としては驚くほどの長寿でした。彼女の遺骨は、自らが建立した瑞龍寺や善正寺、そして縁のあった本圀寺などに分骨されたと伝えられています。
日秀尼が生きた時代の意味と現代へのつながり
日秀尼の生涯は、戦国の世の厳しさ、権力者の家族としての栄光と悲劇、そして深い信仰に生きることで心の平安を求めようとした一人の女性の姿を私たちに教えてくれます。
彼女は、弟・秀吉の天下取りという激流の中で、息子たちを次々と権力の中枢に送り込みました。しかし、その結果として待っていたのは、想像を絶する悲劇でした。もし秀頼が生まれなければ、もし秀次がもっと巧みに立ち回っていたら…歴史に「もし」はありませんが、彼女の苦悩を思うと、様々なことを考えさせられます。
しかし、日秀尼はただ悲嘆に暮れるだけではありませんでした。出家し、寺院を建立することで、亡き者たちの冥福を祈り、そして残された人々のために尽くしました。特に瑞龍寺は、その後も皇女や公家の女性たちの信仰の場として続き、日本の文化に貢献したことは特筆すべきでしょう。
また、興味深いことに、日秀尼の次男・秀勝の娘である完子(さだこ/かんこ)は、五摂家筆頭の公家・九条家に嫁ぎました。そして、その血筋は後の天皇家に繋がっているとされ、日秀尼は現代の皇室とも遠い縁で結ばれているのです。歴史の糸は、思わぬところで繋がっているものです。
日秀尼ゆかりの地である京都の善正寺や、滋賀県近江八幡市の瑞龍寺を訪れると、彼女が生きた時代やその祈りに、より深く触れることができるかもしれません。
おわりに
豊臣秀吉の姉、とも(日秀尼)。彼女の生涯は、歴史の教科書で大きく取り上げられることは少ないかもしれません。しかし、彼女の人生は、豊臣家の興亡という大きな歴史のうねりの中で、一人の女性として、母として、そして信仰者として、力強く生き抜いた証そのものです。
栄華を極めた一族の中で経験した悲劇を乗り越え、92年の長寿を全うした日秀尼。彼女の生き様は、私たちに、絶望的な状況にあっても希望を失わず、自分なりの方法で祈り、行動することの大切さを教えてくれているのかもしれません。
この記事を通して、豊臣秀吉の影に隠れがちな、しかし非常に重要で魅力的な女性、日秀尼の存在を少しでも身近に感じていただけたなら幸いです。








