- 戦国BANASHI TOP
- 歴史・戦国史の記事一覧
- 明智光秀と豊臣兄弟の意外な関係とは?本能寺の変だけじゃない!知将・明智光秀の実像と謎に迫る
明智光秀と豊臣兄弟の意外な関係とは?本能寺の変だけじゃない!知将・明智光秀の実像と謎に迫る
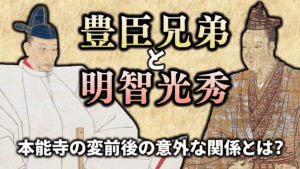
戦国時代最大のミステリー「本能寺の変」。その中心人物である明智光秀(あけちみつひで)は、主君・織田信長を討った「謀反人(むほんにん)」としてあまりにも有名です。
しかし、その一方で、優れた武将であり、教養豊かな文化人でもあった光秀。彼の実像は、本能寺の変の衝撃に隠れがちです。
この記事では、明智光秀の生涯を辿りながら、彼の功績や人物像、そして本能寺の変の真相、さらには豊臣秀吉(とよとみひでよし)・秀長(ひでなが)兄弟との関係にも光を当て、さらに深く光秀を知るための一助となる情報をお届けします。
目次
謎に包まれた前半生と織田信長への仕官
明智光秀の出自や生年は、実は正確にはわかっていません。美濃国(みののくに、現在の岐阜県南部)の土岐(とき)氏の一族という説が有力ですが、確たる証拠はなく、その前半生は謎に包まれています。
若い頃は斎藤道三(さいとうどうさん)に仕えていたものの、道三が息子の義龍(よしたつ)に討たれた「長良川(ながらがわ)の戦い」の後、浪人となり、越前国(えちぜんのくに、現在の福井県北東部)の朝倉義景(あさくらよしかげ)を頼ったと言われています。
光秀の確かな史料が登場するのは40代からで、まさに「遅れてきたヒーロー」ならぬ「遅れて記録に登場した武将」と言えるかもしれません。
彼が歴史の表舞台に躍り出るきっかけとなったのは、室町幕府15代将軍・足利義昭(あしかがよしあき)と織田信長を結びつける役割を果たしたことでした。
光秀は、義昭の上洛(じょうらく、京都へ行くこと)を助ける中で信長と出会い、その才能を見出され、義昭と信長の両方に仕えるという、現代で言えば「兼業(けんぎょう)」のような形でキャリアをスタートさせました。
織田家臣としての輝かしい功績~文武両道の「できる男」~
織田信長に仕えた光秀は、その多才ぶりを遺憾なく発揮します。
軍事面では、近畿各地の平定戦で活躍。特に困難を極めた丹波攻略(たんばこうりゃく、現在の京都府中部・兵庫県北東部の平定)では、5年近くに渡る粘り強い戦いの末にこれを成し遂げ、信長から高く評価されました。
また、金ヶ崎(かねがさき)の退き口(のきくち)では、朝倉・浅井軍の追撃を受ける信長軍の殿(しんがり、退却する軍の最後尾で敵の追撃を防ぐ部隊)という非常に危険な任務を、木下藤吉郎(きのしたとうきちろう、後の豊臣秀吉)らと共に務め、見事成功させています。これは、光秀と秀吉が協力した数少ない記録の一つと言えるでしょう。
行政面での手腕も卓越していました。
京都所司代(きょうとしょしだい)として、都の治安維持や朝廷との交渉を担当。坂本城(滋賀県大津市)、亀山城(京都府亀岡市)、福知山城(京都府福知山市)などを築き、領地経営にも優れた才能を見せました。
特に亀山城下では、地子銭(じしせん、土地税の一種)を免除するなど善政を敷き、領民から慕われたと伝えられています。
また、「明智光秀家中軍法(あけちみつひでかちゅうぐんぽう)」あるいは「明智光秀家中法度(かちゅうはっと)」とも呼ばれる法令を残したとされ、その内容は家臣の権利をある程度認めるなど、当時としては先進的なものであったと言われています。現代で言えば、企業の「コンプライアンス規定」のようなものかもしれません。
さらに光秀は、和歌や連歌(れんが、複数人で和歌の上の句と下の句を詠み繋いでいく詩歌)、茶の湯にも造詣が深い教養人でした。
その中で本能寺の変直前に、京都の愛宕山(あたごやま)で催した連歌会で詠んだ「時は今 あめが下しる 五月哉(さつきかな)」という発句(ほっく、連歌の最初の句)は、彼の謀反の決意を秘めたものだったのではないかと、後世様々に解釈されています。これは「愛宕百韻(あたごひゃくいん)」として有名です。
茶の湯においては、当代一流の茶人・津田宗及(つだそうきゅう)とも親交があり、茶会を催した記録も残っています。ただし、信長から名物の茶道具を拝領する機会は少なかったようで、その点が信長との関係に影響したという説も、一部では囁かれています。
本能寺の変~光秀はなぜ信長を討ったのか?~
天正10年(1582年)6月2日早朝、光秀は中国地方で毛利氏と戦っていた羽柴秀吉(はしばひでよし、後の豊臣秀吉)の援軍に向かうと見せかけて、軍勢を京都に向けました。本能寺に僅かな側近と滞在していた主君・織田信長を急襲し、自害に追い込み、さらに信長の嫡男・信忠も自害に追い込みました。これが世に言う「本能寺の変」です。
光秀が謀反に至った動機については、古来より様々な説が唱えられており、歴史ファンの間でも議論が絶えません。
- 怨恨説(えんこんせつ):信長から受けた屈辱的な仕打ちに対する恨みが原因とする説。親族を処刑された、領地替えを命じられたなどは江戸時代の軍記物や説話の域を出ず、同時代の一次資料では確認はできません。
- 野望説:天下統一の野望を抱いたとする説。これも動機を示す直接の史料はありません。
- 足利義昭黒幕説:追放された将軍・足利義昭が、信長打倒を光秀に命じたとする説。
- 朝廷黒幕説:信長の圧迫に危機感を抱いた朝廷が、光秀を動かしたとする説。
義昭自身の書状など一次史料に光秀と内通した証拠は見出されていません。
近年、特に有力視されているのが「四国説」です。
当時、信長は四国の長宗我部元親(ちょうそかべもとちか)の扱いを巡って方針を転換しました。光秀の家臣である斎藤利三(さいとうとしみつ)は長宗我部氏と縁戚関係にあり、光秀自身も元親との外交交渉を担当していたため、信長の方針転換は光秀の面目を潰し、立場を危うくするものでした。
この外交の急な方針転換と、信長の非情な仕打ちに対する不満が複合的に絡み合い、謀反へと踏み切らせたのではないかと考えられています。特に『石谷家文書(いしがいけもんじょ)』という史料の発見は、この四国説を補強するものとして注目されています。
しかし、光秀自身が動機を語った信頼できる記録は残っておらず、真相は依然として謎のままです。この「ミステリアスさ」もまた、光秀が人々を惹きつけてやまない理由の一つかもしれません。
光秀と豊臣兄弟~変以前の希薄な関係と変後の激突~
本能寺の変以前の光秀と秀吉の直接的な関係を示す一次史料は、実はそれほど多くありません。
先述の通り、金ヶ崎の退き口で共に殿(しんがり)を務めた記録や、京都の政務を一時的に共同で担当したとされるなど、織田家の重臣として協力する場面はあったようです。
しかし、両者の間に深い個人的な親交があったか、あるいは逆に対立関係にあったかを示す具体的な書簡のやり取りやエピソードは、現在のところ確実なものは見つかっていません。
お互いをライバルとして意識していた可能性はありますが、それはあくまで状況からの推測の域を出ないと言えるでしょう。
秀吉の弟豊臣秀長(羽柴秀長)に至っては、光秀との直接的な接点を示す史料はさらに乏しく、本能寺の変以前にどのような関係にあったかは、ほとんどわかっていません。
秀長は兄・秀吉の有能な補佐役として知られますが、光秀との間に特筆すべきエピソードは記録されていないのが現状です。
本能寺の変の報せは、備中高松城(びっちゅうたかまつじょう)で毛利氏と対峙していた秀吉のもとに、変が起こった翌日の6月3日夜から4日未明という驚くべき速さで届きます。
秀吉はただちに毛利氏と和睦を結び、京都へ向けて全軍を反転させました。これが有名な「中国大返し(ちゅうごくおおがえし)」です。
この電光石火の行動には、秀吉の情報収集能力の高さや、弟・秀長の内政手腕による後方支援体制の確立が大きく貢献したと言われています。まさに兄弟の「阿吽(あうん)の呼吸」がなせる業だったのかもしれません。
そして、天正10年(1582年)6月13日、光秀軍と秀吉軍は山城国(やましろのくに、現在の京都府南部)の山崎(やまざき)で激突します(山崎の戦い)。
兵力では秀吉軍が優勢でした。秀吉は巧みな情報操作で味方を増やし、光秀は期待していた他の織田家臣の加勢を得られず、孤立していきます。
戦いは、摂津国(せっつのくに)と山城国の境にある天王山(てんのうざん)の争奪戦が鍵となりました。秀吉軍は、中川清秀(なかがわきよひで)や高山右近(たかやまうこん)らの活躍で天王山を確保し、戦いを有利に進めます。
豊臣秀長もこの戦いに参陣し、一軍を率いて奮戦したとされていますが、その具体的な戦功を詳細に記した一次史料は限られています。しかし、兄を支え、秀吉軍の統率に貢献したことは間違いないでしょう。
戦術に優れ、鉄砲隊の運用にも長けていた光秀でしたが、兵力差や地理的制約、そして何よりも「主君殺し」という汚名による人心の離反が響き、敗北を喫します。
敗走した光秀は、近江国(おうみのくに、現在の滋賀県)へ逃れる途中、小栗栖(おぐるす、現在の京都市伏見区)の竹藪で落ち武者狩りの農民に襲われ、命を落としたと言われています。享年は50代半ばから60代とされていますが、正確な年齢も不明なままです。
光秀の天下はわずか10数日、「三日天下」とも揶揄(やゆ)される短いものでした。
明智光秀の歴史的評価と後世への影響
本能寺の変という衝撃的な事件により、「謀反人」「逆臣」というイメージが強い明智光秀。
江戸時代の軍記物などでは、そのように描かれることが多かったようです。しかし、近年では、光秀の優れた行政手腕や教養、先進的な思考などが再評価される動きも活発です。
領地経営で見せた善政や、家臣を大切にした逸話、そして本能寺の変の動機についても、怨恨や野望といった単純なものではなく、当時の複雑な政治状況や光秀自身の苦悩があったのではないか、と多角的に研究されています。
呉座勇一氏などの研究者は、光秀を「教養豊かな常識人」と評価する一方で、信長の非道な行いを阻止しようとしたという「義憤説(ぎふんせつ)」や、あるいはやはり天下取りの野望があったとする説など、様々な角度から光秀像に迫っています。
また、創元社から出版されている『江戸時代の明智光秀』という書籍では、江戸時代の人々が光秀をどのように捉え、語り継いできたのか、その多様な光秀像が紹介されており、興味深いものがあります。
例えば、光秀が落ち延びて生き続けたという「生存説」や、各地に残る「光秀の首塚」の伝承なども、人々の光秀への関心の高さを物語っています。
本能寺の変がなければ、その後の日本の歴史は大きく変わっていたでしょう。
光秀の行動は、結果的に豊臣秀吉の台頭を早め、豊臣政権の成立、そして江戸幕府へと続く日本の歴史の大きな転換点となりました。
光秀の真意はどうであれ、彼が歴史に与えた影響は計り知れません。
まとめ~明智光秀の多面的な魅力に触れる~
明智光秀は、本能寺の変という一点だけで語られがちな人物ですが、その生涯を詳しく見ていくと、優れた武将、有能な行政官、そして深い教養を持つ文化人という、実に多面的な魅力を持った人物であったことがわかります。
豊臣秀吉・秀長兄弟との関係は、本能寺の変を境に劇的に変化し、その後の歴史を大きく動かしました。変以前の関係性については史料が乏しく謎が多いものの、それもまた歴史のロマンと言えるかもしれません。
本能寺の変の動機は、これからも多くの歴史ファンを惹きつけ、様々な議論が交わされていくことでしょう。
この記事が、明智光秀という複雑で魅力的な人物を、より深く理解するための一助となれば幸いです。








