- 戦国BANASHI TOP
- 歴史・戦国史の記事一覧
- 長宗我部元親!土佐の出来人、!長宗我部元親の夢と豊臣秀吉との激闘
長宗我部元親!土佐の出来人、!長宗我部元親の夢と豊臣秀吉との激闘
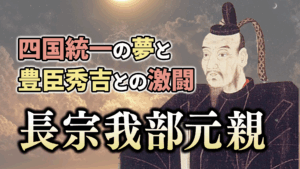
戦国時代、数多の英雄たちが覇を競い合いましたが、その中でも特に異彩を放つ武将がいました。その名は長宗我部元親(ちょうそかべ もとちか)。
「ちょうそがべ」と間違えやすい? いえいえ、正しくは「ちょうそかべ」です。現代でもしばしば読み方を間違えられるこの名前の主は、土佐(現在の高知県)の小領主から身を起こし、一時は四国全土をその手中に収めようとした、まさに「土佐の出来人(できじん)」(土佐が生んだ傑出した人物)でした。
幼少期は「姫若子(ひめわこ)」と揶揄(やゆ)されるほど内気だった元親が、いかにして「鬼若子(おにわこ)」と恐れられる勇将へと変貌を遂げ、四国の覇者へと駆け上がったのか。そして、天下一統を進める豊臣秀吉という巨大な壁にどう立ち向かい、どう生き抜いたのか。
この記事では、そんな長宗我部元親の波乱に満ちた生涯と、特に宿敵であり、後に主君ともなる豊臣秀吉・秀長兄弟との関係に焦点を当てながら、その歴史的重要性に迫ります。歴史好きのあなたならきっと、元親の魅力に引き込まれることでしょう!
長宗我部元親は、1539年(天文8年)、土佐の戦国大名・長宗我部国親(くにちか)の嫡男として岡豊城(おこうじょう)で生を受けました。 そんな元親が劇的な変化を遂げたのは、22歳で迎えた初陣、長浜の戦いでした。 1560年(永禄3年)に父・国親が病死すると、元親は家督を相続。ここから、彼の快進撃が始まります。 「一領具足」とは、普段は田畑を耕す農民でありながら、戦の際には一領(いちりょう=一揃い)の具足(鎧兜)と武器を持って馳せ参じる半農半兵の兵士たちのことです。<彼らは土地との結びつきが強く、郷土防衛の意識も高かったため、非常に精強な軍団だったと言われています。 1575年(天正3年)の渡川(四万十川、しまんとがわ)の戦いで土佐一条(いちじょう)氏を破り、ついに元親は悲願の土佐統一を成し遂げます。一介の国人領主(こくじんりょうしゅ=在地領主)に過ぎなかった長宗我部氏が、土佐一国を支配する大名へと成長したのです。 目次 土佐を統一した元親の目は、当然ながら四国の残りの三国、阿波(あわ=徳島県)、讃岐(さぬき=香川県)、伊予(いよ=愛媛県)へと向けられました。 「鳥なき島の蝙蝠(こうもり)」などと揶揄されることもあった元親ですが、その戦略眼と実行力は本物でした。 従来、長宗我部元親は四国統一を成し遂げたとされてきましたが、近年の研究では、四国のそれぞれの国で統一を達成できていなかったことが指摘されています。1584年(天正12年)、織田信雄(おだのぶかつ)と徳川家康が羽柴秀吉(はしばひでよし)と戦う小牧・長久手の戦いが勃発します。このとき、元親は家康から秀吉の拠点である大坂を背後から脅かすよう依頼を受けます。しかし、讃岐国虎丸(とらまる)城(香川県東かがわ市)と阿波国土佐泊(とさどまり)城(徳島県鳴門市)の攻略に手間取り、この二城は最後まで攻略できませんでした。また、伊予国で敵対していた河野通直(こうのみちなお)も最後まで降伏していませんでした。 元親が四国統一に苦戦していた頃、中央の情勢は大きく動いていました。 元親は、当初織田信長と同盟関係にありましたが、信長の四国政策の変更により関係が悪化。信長による四国遠征軍がまさに派遣されようとした矢先に本能寺の変が起こり、九死に一生を得たという経緯があります。 秀吉が元親を敵視した理由については諸説ありますが、一説には、元親が本能寺の変の首謀者である明智光秀と親密な関係にあったためとも言われています(ただし、これはあくまで俗説の域を出ません)。 小牧・長久手の戦いが終結したことにより、元親は外交上孤立してしまいます。そこで、元親は讃岐・阿波を差し出す代わりに伊予を貰おうとしましたが、伊予を求める毛利氏との兼ね合いが問題となりました。こうして、元親と秀吉の交渉は決裂し、ついに武力衝突へと発展します。 1585年(天正13年)6月末、秀吉は弟の豊臣秀長(とよとみひでなが)を総大将とする、総勢10万を超える大軍を四国へ派遣します。これが「四国出兵(しこくしゅっぺい)」です。 【ここでワンポイント解説:豊臣秀長とは?】 豊臣軍は、阿波、讃岐、伊予の三方から四国へ上陸。対する長宗我部軍の兵力は約4万。圧倒的な兵力差と、毛利輝元(もうりてるもと)、小早川隆景(こばやかわたかかげ)、宇喜多秀家(うきたひでいえ)といった名だたる武将を揃えた豊臣軍の前に、長宗我部軍は各地で敗退を重ねます。 元親は、四国の玄関口である阿波の岩倉城(いわくらじょう)を拠点に抵抗を試みますが、豊臣軍の猛攻の前に持ちこたえることはできませんでした。 降伏の条件として、元親は阿波・讃岐・伊予の三国を没収され、土佐一国のみを安堵されることになりました。 秀吉に臣従した元親は、豊臣政権下の一大名として生きることを余儀なくされます。 しかし、この九州の地で、長宗我部家に最大の悲劇が訪れます。 その後も元親は、1590年(天正18年)の小田原合戦、そして文禄・慶長の役(朝鮮出兵)にも水軍を率いて参陣するなど、豊臣政権下で忠実に任務を果たしました。 武勇ばかりが注目されがちな元親ですが、領国経営においても優れた手腕を発揮しました。 その代表的なものが「長宗我部地検帳(ちょうそかべじけんちょう)」の作成です。 また、元親は「長宗我部元親百箇条(ちょうそかべもとちかひゃっかじょう)」と呼ばれる分国法(ぶんこくほう=戦国大名が領国支配のために定めた法律)を制定したことでも知られています。 文化面では、儒学(じゅがく)の一派である南学(なんがく)を奨励したとされ、土佐の文化発展にも貢献したと言われています。ただし、これについては詳細な史料が乏しく、今後の研究が待たれるところです。 嫡男・信親を失ったことは、元親の晩年、そして長宗我部家の運命に大きな影響を与えました。 この判断には、亡き信親の娘を盛親に娶(めあわ)せることで、信親の血筋を繋ごうとした元親の想いがあったと言われています。 1598年(慶長3年)に豊臣秀吉が死去すると、国内の情勢は再び緊迫。そんな中、1599年(慶長4年)5月、長宗我部元親は京都伏見の屋敷で波乱に満ちた61年の生涯を閉じました。 元親の死後、家督を継いだ盛親は、翌1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いで西軍に与します。 長宗我部元親は、歴史家や歴史ファンの間で様々な評価がなされる武将です。 しかし、確かなことは、彼が戦国という厳しい時代を全力で生き抜き、地方の雄として中央の巨大な権力に果敢に挑んだ、類まれなる指導者であったということです。 現代の高知県では、長宗我部元親は郷土の英雄として深く敬愛されています。 「姫若子」から「鬼若子」へ、そして四国の最有力者へ。挫折と栄光、そして悲劇を経験しながらも、最後まで己の道を貫こうとした長宗我部元親。彼の生き様は、現代を生きる私たちにも、多くの示唆を与えてくれるのではないでしょうか。 長宗我部元親の生涯は、まさに戦国乱世を象徴するような、激動と波乱に満ちたものでした。 彼の人生は、成功の陰には常に困難が潜んでいること、そして、一つの悲劇が時として大きな組織の運命をも左右してしまうことを教えてくれます。 この記事を通して、長宗我部元親という一人の武将の魅力、そして彼が生きた時代の奥深さを少しでも感じていただけたなら幸いです。 津野倫明『人をあるく 長宗我部元親と四国』(吉川弘文館、2014年) ◆編集者:相模守
しかし、幼い頃の元親は色白で大人しく、武芸よりも書物を好むような少年だったと言われています。その姿から「姫若子」と呼ばれ、父・国親や家臣たちはその将来を案じたとも伝えられています。現代で言えば、「ちょっと頼りないお坊ちゃん」といったところでしょうか。
父・国親の厳命により出陣した元親は、まるで別人のような勇猛果敢な戦いぶりを見せ、自ら槍を振るって敵兵を討ち取ったのです。この活躍により、周囲の評価は一変。「姫若子」は「鬼若子」へと生まれ変わった瞬間でした。
元親は、まず土佐国内の統一に着手。巧みな外交戦略と、当時としては革新的だった兵農分離システム「一領具足(いちりょうぐそく)」を駆使し、次々と敵対勢力を打ち破ったとされてきました。しかし近年の研究では、当時の史料には「一領具足」がほとんど確認されないため、その実態を再検討する研究が行われています。 ここでワンポイント解説:一領具足とは?
破竹の勢い!四国統一の夢へ
阿波では三好(みよし)氏の内紛に乗じて勢力を拡大。讃岐、伊予へも積極的に兵を進めます。特に伊予では、金子元宅(かねこもといえ)ら在地勢力と結びつきながら、巧みに勢力を浸透させていきました。
とはいえ、この時が、元親の生涯における絶頂期と言えるでしょう。 中央の覇者、豊臣秀吉との対峙
1582年(天正10年)の本能寺の変で織田信長が倒れると、その実質的な後継者として急速に台頭してきたのが、羽柴(豊臣)秀吉です。
信長亡き後の混乱に乗じて四国統一を推し進めた元親でしたが、天下一統を目指す秀吉にとって、四国に一大勢力を築いた元親は、看過できない存在となっていきました。
また、元親が秀吉と敵対する勢力(柴田勝家や徳川家康・織田信雄など)と連携する動きを見せたことも、秀吉の警戒心を強めた要因と考えられます。 四国出兵!秀吉の弟・秀長と元親の降伏
豊臣秀長は、秀吉の異父弟(または同父弟とも)。兄・秀吉の天下統一事業を冷静沈着に補佐し続けた名将です。温厚篤実な人柄で人望も厚く、秀吉政権の「ナンバー2」として、政治・軍事両面で多大な功績を上げました。「秀長がいなければ秀吉の天下はなかった」とまで評価される人物です。
戦況の不利を悟った元親は、同年7月下旬、ついに秀吉に降伏します。
わずか数ヶ月前まで四国の大部分を治めていた元親にとって、これは屈辱的な結果だったかもしれません。しかし、完全に改易(かいえき=領地没収・武士の身分剥奪)されることなく、本拠地である土佐の領有を認められたのは、秀吉の温情だったという見方もできます。一説には、秀長が元親の武勇を惜しみ、秀吉に寛大な処置を進言したとも言われています。 豊臣政権下での苦難と悲劇
翌1586年(天正14年)、秀吉による九州出兵が始まると、元親も嫡男の長宗我部信親(ちょうそかべのぶちか)と共に従軍を命じられます。
豊後(ぶんご=大分県)の戸次川(へつぎがわ)で島津軍と衝突した際、豊臣軍の軍監(ぐんかん=総大将の補佐役)であった仙石秀久(せんごくひでひさ)の無謀な作戦により豊臣軍は窮地に陥ります。この戦いで、元親が将来を嘱望していた信親が、わずか22歳の若さで討死してしまうのです(戸次川の戦い)。
しかし、その胸中には、かつての四国統一の夢、そして愛息・信親を失った悲しみが常に渦巻いていたのかもしれません。 元親の領国経営と文化
これは、領内の田畑の面積、等級、耕作者などを詳細に調査・記録したもので、年貢(ねんぐ)徴収の基準を明確化し、兵役の基盤を固めることを目的としており、当時の領国経営を知る上で非常に重要な史料となっています。いわば、領国版の「国勢調査+固定資産台帳」のようなものでしょうか。
この百箇条には、家臣の心得から農民の生活規範、訴訟のルールに至るまで、多岐にわたる規定が盛り込まれていました。この分国法は慶長の役の直前に制定されたもので、朝鮮侵略が大きな契機となったとされています。後継者問題と晩年、そして長宗我部家の終焉
元親は、信親亡き後、次男の香川親和(かがわちかかず)や三男の津野親忠(つのちかただ)ではなく、四男の長宗我部盛親(もりちか)を後継者に指名します。
しかし、この家督相続は家中に大きな波紋を呼びました。特に、信親に次ぐ器量人として期待されていた津野親忠を支持する勢力は反発し、元親は反対派の重臣であった甥の吉良親実(きらちかざね)らを粛清しています。この事件を現代の我々は、一族を排除するような手段をとった元親の暴走と見てしまいがちですが、一族や家臣を排除する手段は長宗我部家に限った話ではありません。戦国大名というと当主が絶対的な権限を有していたように見えますが、実際には一族や家臣が意思決定に関わることがよく見られました。天下人となった豊臣秀吉はこうした状況を問題視し、大名当主がリーダーシップを取っていくことを求めました。家臣たちを統制できない大名は、最悪の場合改易されることがありました。つまり、元親は長宗我部家が大名として存続するために、自身の甥である吉良親実を排除したと言えるでしょう。
しかし、西軍は敗北。戦後、盛親は改易され、長宗我部氏は大名としての地位を失ってしまいます。元親が築き上げた長宗我部家の栄華は、その死からわずか1年余りで幕を閉じることになったのです。 長宗我部元親の歴史的評価と現代に遺るもの
土佐の一国人から身を起こし、一時は四国を統一するまでに勢力を拡大した英雄として称賛される一方で、信親の死後の冷酷な処置や後継者問題の混乱ぶりから、悲劇の武将、あるいは晩節を汚した人物として語られることもあります。
その巧みな外交戦略、革新的な軍事制度、そして領国経営の手腕は、現代においても学ぶべき点が多いと言えるでしょう。
高知市内には勇ましい元親の銅像が立ち、ゆかりの地では祭りも開催されるなど、その遺徳は今もなお語り継がれています。 まとめ
四国統一という大きな夢を抱き、それを目前にしながらも、時代の大きなうねりの中で翻弄され、ついにはその夢を絶たれてしまいます。しかし、その不屈の精神と卓越したリーダーシップは、今も多くの人々を魅了してやみません。
歴史のifを語ることはできませんが、もし嫡男・信親が生きていたら、もし豊臣秀吉との関係が違ったものであったなら…長宗我部元親と長宗我部家の運命は、また別の道を辿っていたのかもしれませんね。
平井上総『長宗我部元親・盛親』(ミネルヴァ書房、2016年)
平井上総「長宗我部元親ー天下人と戦った四国一の大名」(平井上総編『戦国武将列伝10四国編』戎光祥出版、2023年)








