- 戦国BANASHI TOP
- 歴史上の人物の記事一覧
- 【豊臣秀吉】農民から天下人へ駆け上がった男の生涯と、影で支えた弟・秀長の功績
【豊臣秀吉】農民から天下人へ駆け上がった男の生涯と、影で支えた弟・秀長の功績
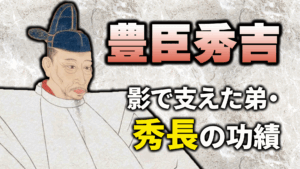
日本の歴史上、最もドラマチックな出世を遂げた人物の一人、豊臣秀吉(とよとみひでよし)。戦国乱世に農民の子として生まれながら、知略と行動力、そして類まれなる「人たらし」の才能で天下一統を成し遂げました。彼の生涯は、まさに波乱万丈。その輝かしい成功の陰には、実務能力に長けた弟・豊臣秀長(とよとみひでなが)の献身的な支えがありました。この記事では、天下人・秀吉の軌跡と、彼を支え続けた「もう一人の天下人」秀長の功績、そして豊臣政権の光と影に迫ります。
目次
出自と立身出世:日輪の子、大空へ
天文5年、若しくは6年(近年は天文6年説が主流)に尾張国中村(おわりのくになかむら、現在の愛知県西部)の貧しい農民(あるいは下級武士とも)の子として生まれたとされる秀吉。幼名は日吉丸(ひよしまる)、後に木下藤吉郎(きのしたとうきちろう)と名乗ります。出自については諸説あり、正確な記録は多くありません。しかし、その出自の低さこそが、後の彼の成り上がり物語をより一層際立たせることになります。
若き日の秀吉は、針売りをしながら諸国を渡り歩いたとも、今川家の家臣・松下之綱(まつしたゆきつな)に仕えたとも伝えられています。彼が歴史の表舞台に本格的に登場するのは、織田信長(おだのぶなが)に仕えてからです。信長の草履取り(ぞうりとり)であった際、寒い冬に懐で草履を温めて差し出したという逸話は有名ですが、これは後世の創作という説が有力です。また、有名な墨俣一夜城の築城に関しても俗説を裏付ける史料はありません。しかし、こうした逸話が生まれるほど、秀吉が信長の信頼を得るために機転を利かせ、細やかな気配りをしていたことは想像に難くありません。
秀吉の姿が史料に現れるのは永禄8年からです。この年の11月2日に秀吉は美濃松倉城主坪内利定に622貫文の知行を宛行っています(「坪内文書」)。このことから、この時期の秀吉はおおよそ美濃・尾張辺りに所領を持っており、織田家の中でそれなりの地位にあったことが考えられますが、詳細は不明です。ただ、いずれにせよ何の伝手もない農民の子が織田家臣として認められるためには相当の努力が必要だったことでしょう。後年、関白になってからも、公家社会の作法やしきたりを懸命に学んでいます。彼の向上心は生涯を通じて衰えることはなかったようです。秀吉が日本一の出世人と評される所以は人心掌握術(じんしんしょうあくじゅつ)や交渉力、そして前例にとらわれない柔軟な発想にあったと言えるでしょう。まさに、現代のビジネスシーンにも通じる「プロジェクトマネージャー」としての手腕を発揮していたのかもしれません。
信長の死後と天下一統への道:激動の時代を駆け抜ける
天正10年(1582年)、本能寺の変で主君・信長が明智光秀(あけちみつひで)に討たれるという衝撃的な事件が起こります。当時、備中高松城(びっちゅうたかまつじょう)で毛利軍と対峙していた秀吉は、この報に接すると、驚くべき速さで毛利氏と和睦。すぐさま京へ軍を返し、山崎の戦いで光秀を討ち破ります。この「中国大返し(ちゅうごくおおがえし)」と呼ばれる迅速な行動は、秀吉の判断力と実行力を示すエピソードとして名高いです。「神業」とも言われる秀吉の中国大返しですが、あまりにも迅速な秀吉の行動から、巷では「本能寺の変 秀吉黒幕説」などといったものも取沙汰されています。結論から言うと、この「秀吉黒幕説」は当時の秀吉の状況を見る限り非常に考えにくいです。「秀吉黒幕説」が取沙汰される理由として、「信長が光秀に討たれて最も利を得たのは秀吉だ」とするものがあります。しかし、光秀を討ったからといって織田家の筆頭家老の地位が確約されている訳でも、ましてや天下人になれる訳でもありません。毛利に嘘の情報を流し、停戦協定を結んでいたとは言え、信長の死が毛利方に伝わるのは時間の問題。そうなると京に引き返す秀吉の軍は背後から毛利方の追撃を受ける可能性も考えられます(実際には追撃を受けておらず、毛利側としてもそこまでして織田家の内部抗争に介入する理由はなかったと思われますが)。そもそも信長はこの時点で家督を長男の信忠に譲っており、信忠亡き後はその子、つまり信長の嫡孫である三法師(後の織田秀信)が織田家を継ぐというのが規定路線であったと思われます。こういった状況の中で、光秀討伐の実績のみを振りかざし、織田家の筆頭家老に踊り出ることは不可能です。また、近年の研究では、その速度や兵站(へいたん、戦闘部隊の後方支援活動)について、従来言われていたほどの「神業」ではなかった可能性も指摘されています。しかし、主君の仇を討ったことで、秀吉は織田家中の主導権争いで一気に優位に立ちました。
その後、信長の後継者を決める清洲会議(きよすかいぎ)を経て、織田家筆頭家老であった柴田勝家(しばたかついえ)との対立が深まります。そして天正11年(1583年)、賤ヶ岳(しずがたけ)の戦いが勃発。この戦いで秀吉は勝家を破り、名実ともに信長の後継者としての地位を確立しました。この合戦の勝因の一つとして、秀吉の巧みな情報戦略や、敵将の調略(ちょうりゃく、敵を味方に引き入れること)が挙げられます。
しかし、天下一統への道はまだ半ばです。天正12年(1584年)には、織田家を蔑ろにするような秀吉の横暴ぶりに耐えかねた織田信雄(おだのぶかつ)が・徳川家康(とくがわいえやす)と手を組み秀吉と対峙します。所謂小牧・長久手(こまき・ながくて)の戦いの勃発です。戦術的には家康に苦杯を喫する場面もありましたが、最終的には信雄の方から秀吉に単独講和を持ちかけ、戦いは終結。この後、秀吉の手引きもあり、信雄は正三位権大納言に叙されます。秀吉自身は正二位内大臣となり、朝廷の権威を持って織田家を上回り、この時をもって秀吉の下剋上が完成されました。ちなみに信雄自身は徳川の時代まで生きながらえ、家康からも破格に遇されています。彼もまた秀吉に負けず劣らずの世渡り上手な人物でした。秀吉はその後、紀州(きしゅう、現在の和歌山県など)、四国、九州と次々に平定を進め、天正18年(1590年)、関東の雄・北条氏を小田原征伐で破り、ついに天下統一を成し遂げました。
豊臣政権の確立と主要政策:天下人の描いた国家像
天下人となった秀吉は、強力な中央集権体制を築き上げるため、様々な政策を打ち出します。
まず、朝廷との関係を重視し、天正13年(1585年)には近衛前久の猶子となり(藤原秀吉)関白(かんぱく、天皇を補佐する最高職)に、翌年には豊臣の姓を賜り、藤原姓を豊臣に改めました。ここに源平藤橘に並ぶ新たな姓が誕生しました。また、同時に太政大臣(だじょうだいじん)にも任ぜられます。これにより、秀吉は武力だけでなく、伝統的な権威も手中に収めました。大坂城を築城し、聚楽第(じゅらくだい)を建設して後陽成天皇(ごようぜいてんのう)を迎えるなど、その権勢を内外に示しました。
内政においては、「太閤検地(たいこうけんち)」と「刀狩(かたながり)」が特に有名です。太閤検地は、全国の田畑の面積や収穫量を統一した基準で測量し、石高(こくだか、土地の生産性を米の量で示したもの)を確定させるものでした。これにより、年貢(ねんぐ)徴収のシステムが整備され、大名の領国支配のあり方も大きく変わりました。荘園(しょうえん)制度の解体にも繋がり、近世的な土地所有制度への移行を促したと言えます。
一方、刀狩は、農民から刀や槍などの武器を没収する政策です。表向きは方広寺(ほうこうじ)の大仏造立のための釘や鎹(かすがい)にするという名目でしたが、真の目的は兵農分離(へいのうぶんり、武士と農民の身分を明確に分けること)を進め、農民による一揆(いっき)を防ぐことにありました。これにより、武士は戦闘に専念し、農民は農業に専念するという社会構造が強化されました。ただし、武器の完全な没収は難しく、その後も農民の武装蜂起が皆無になったわけではありません。
また、全国の大名に対し「惣無事令(そうぶじれい)」を発令し、大名間の私的な戦闘を禁じました。これは、豊臣政権が全国の平和維持の責任を負うことを宣言するものであり、従わない大名は討伐の対象となりました。これにより、長らく続いた戦国時代は名実ともに終焉を迎えることになります。
豊臣秀長:兄を支えた「もう一人の天下人」
秀吉の天下一統事業と豊臣政権の安定に、弟・豊臣秀長の存在は不可欠でした。秀長は、秀吉とは異父兄弟(一説では同父兄弟)とも言われ、温厚篤実(おんこうとくじつ、穏やかで誠実なこと)な性格で知られています。兄の才能を早くから見抜き、常に影日向となって支え続けました。
秀長は、武将としても優れた能力を発揮し、数々の戦いで軍功を挙げています。しかし、彼の真骨頂は、むしろ内政手腕や調整能力にありました。秀吉が中央で派手な政策を展開する一方、秀長は大和(やまと、現在の奈良県)郡山(こおりやま)を拠点に、畿内(きない、都周辺の国々)の安定化や、気性の激しい秀吉と諸大名との間の緩衝材(かんしょうざい)としての役割を担いました。「内々の儀は宗易(千利休)、公儀の事は宰相(秀長)に」と当時の人々が語ったように、秀長の政治力と調整能力は、豊臣政権にとってまさに生命線だったのです。
しかし、天正19年(1591年)、秀長は病によりこの世を去ります。彼の死は、秀吉にとって計り知れない打撃となりました。有能な補佐役であり、唯一無二の理解者でもあった弟を失ったことで、豊臣政権は徐々にバランスを崩し始めたと言われています。特に、秀吉の晩年の独善的な政策決定や、後継者問題の混乱には、秀長の不在が大きく影響したのかもしれません。もし秀長が長生きしていれば、豊臣家の運命も変わっていたかもしれない、と評する歴史家も少なくありません。
晩年の秀吉と政権の陰り:栄華の先に待つもの
天下一統を果たし、栄華を極めた秀吉でしたが、その晩年にはいくつかの大きな影が差し始めます。
茶人として知られ、秀吉の側近としても重用された千利休(せんのりきゅう)との関係悪化は、その一つです。利休は、秀吉の黄金の茶室に象徴される派手好みとは対照的に、「侘び寂び(わびさび)」の精神を追求しました。両者の美意識や価値観の相違、あるいは利休の政治的影響力を秀吉が警戒したなど、確執の原因については諸説ありますが、天正19年(1591年)、秀吉は利休に切腹を命じます。この事件は、豊臣政権の文化政策や、秀吉の精神状態の変化を示すものとして注目されています。
そして、秀吉の晩節を汚した最大の失策と言われるのが、二度にわたる朝鮮出兵(文禄・慶長の役、ぶんろく・けいちょうのえき、1592年~1598年)です。明(みん、当時の中国王朝)の征服を目指したこの大規模な海外派兵は、国内外に大きな犠牲と混乱をもたらしました。目的が曖昧なまま強行されたこの戦いは、多くの大名に経済的・人的な負担を強い、日本国内の厭戦気分(えんせんきぶん、戦争を嫌う気持ち)を高めました。また、朝鮮半島にも甚大な被害を与え、後の両国関係に深い傷跡を残すことになります。朝鮮側の記録である『懲毖録(ちょうひろく)』などからは、当時の戦禍の凄まじさが伝わってきます。
国内では、後継者問題も深刻化します。実子・鶴松(つるまつ)を幼くして亡くした秀吉は、甥の豊臣秀次(とよとみひでつぐ)を養子に迎え関白の位を譲りました。しかし、その後、側室の淀殿(よどどの)との間に実子・豊臣秀頼(とよとみひでより)が誕生すると、秀吉は秀頼に政権を継がせることを望むようになります。文禄4年(1595年)、秀吉は秀次に謀反(むほん)の疑いをかけて高野山に追放し、切腹に追い込こんだとされる「秀次事件」ですが、史料を読み解いていくと違った事実が浮かび上がってきます。確かに文禄4年を機に両者の関係が悪化していったことは間違いないと思われます。その直接の原因は分かりませんが、医師の曲直瀬玄朔が後陽成天皇よりも秀次の診察を優先したことが関連しているのではないかと、『図説 豊臣秀吉』の中で歴史学者の柴裕之氏は指摘されています。譜代の家臣のいない秀吉にとって数少ない身内は貴重な存在でした。秀頼を立てつつも、秀次と上手く折り合いをつけながら政権の方向性を模索していたと思われます。ただ、上述の様な問題も起こり、以降は二人の間ですれ違いが起きてしまいます。最終的に秀吉に謀反の疑いをかけられ、高野山に追放されてしまいます。高野山に追放された秀次は自身の無実を証明するため切腹をしますが、これは秀吉に対する最後の抵抗であったのかもしれません。秀吉としても、自身の政権の脆弱さが明るみになることは避けたかったのでしょう。秀次の妾一族を悉く処刑し、聚楽第も破却するという徹底ぶりを世間に見せつけることで、秀次の謀反のプロパガンダを行いました。「秀次事件」の真相については、秀次の不行跡説、秀吉の被害妄想説など様々な見解があり、未だ謎多き事件とされています。この事件は、豊臣政権の有力な後継者を失い、政権内部の動揺を招きました。
秀吉の人物像:光と影
豊臣秀吉は、どのような人物だったのでしょうか。彼の最大の武器は、やはり「人たらし」の才能でしょう。秀吉が発給した文書数は現在確認されるだけでも7000通に及ぶと言います。権力者となってからも非常に筆まめで家臣や家族のことを気にかけていたようです。身分の低い者を抜擢(ばってき)し、敵将すらも味方につける人心掌握術は、彼を天下人の地位に押し上げた大きな要因です。また、常識にとらわれない発想力や、困難な状況を打開する行動力も特筆すべき点です。
一方で、派手好みな一面も持ち合わせていました。黄金の茶室や、豪華絢爛(ごうかけんらん)な大坂城、聚楽第などはその象徴です。しかし、それは単なる成金趣味ではなく、自身の権威を高め、天下人にふさわしい威光を示すための演出であったとも考えられます。また、桃山文化と呼ばれる華やかな文化のパトロン(後援者)でもありました。
しかし、晩年には猜疑心(さいぎしん)が強くなり、独裁的な傾向を見せるようになります。朝鮮出兵の強行や秀次事件などは、その現れと言えるかもしれません。出自に対するコンプレックスが、彼を過剰な権威主義や自己顕示欲に走らせたという見方もあります。死後、自身を神として祀(まつ)らせる「豊国大明神(とよくにだいみょうじん)」への神格化を進めたことにも、その一端がうかがえます。
このように、秀吉は魅力的な「光」の部分と、危うさをはらんだ「影」の部分を併せ持つ、非常に複雑で多面的な人物であったと言えるでしょう。
まとめ:秀吉が残したもの、そして未来へ
慶長3年(1598年)、豊臣秀吉は波乱に満ちた生涯を閉じました。彼の死後、幼い秀頼を巡って五大老(ごたいろう)筆頭の徳川家康が台頭し、豊臣政権は急速に力を失っていきます。そして、関ヶ原の戦いを経て、時代は江戸幕府へと移り変わります。
しかし、秀吉が成し遂げた天下一統と、彼が断行した太閤検地や刀狩などの諸政策は、その後の日本の社会構造に大きな影響を与えました。戦国乱世に終止符を打ち、近世という新たな時代の扉を開いた人物として、その功績は揺らぎません。また、貧しい身から天下人にまで上り詰めた彼の生涯は、「日本史上最大のサクセスストーリー」として、今も多くの人々を惹きつけてやみません。
そして、忘れてはならないのが、兄・秀吉を支え続けた豊臣秀長の存在です。彼の堅実な実務能力と調整力がなければ、秀吉の天下一統はより困難なものになっていたでしょう。歴史の表舞台で輝く英雄の影には、常にそれを支える人々の力が存在することを、豊臣兄弟の物語は教えてくれます。
豊臣秀吉という人物を多角的に見つめ直すことは、現代に生きる私たちにとっても、リーダーシップや組織運営、そして人間関係のあり方について多くの示唆を与えてくれるのではないでしょうか。
編集者
仲程








