- 戦国BANASHI TOP
- 歴史上の人物の記事一覧
- 丹羽長秀の実像に迫る!織田信長が「友であり、兄弟」と呼んだ男~米五郎左と呼ばれた万能武将の生涯とは?~
丹羽長秀の実像に迫る!織田信長が「友であり、兄弟」と呼んだ男~米五郎左と呼ばれた万能武将の生涯とは?~
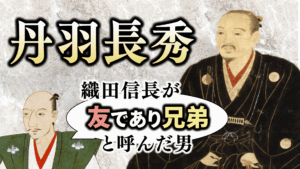
戦国時代という激動の時代を駆け抜けた武将は数多いますが、織田信長、豊臣秀吉という二人の天下人に深く信頼され、その天下統一事業を支えた人物がいます。その名は丹羽長秀(にわ ながひで)。
「米五郎左(こめ ごろうざ)」の異名で知られ、派手さはないものの、組織に不可欠な実務能力と誠実さで乱世を生き抜きました。この記事では、そんな丹羽長秀の生涯と、特に豊臣兄弟との関係に焦点を当て、その知られざる魅力に迫ります。
この記事では、「丹羽長秀ってどんな人?」
「米五郎左ってどういう意味?」
「豊臣秀吉や弟の秀長と仲が良かったの?」といった気になる部分を徹底解説していきます!
目次
丹羽長秀とは?~織田家臣団の「縁の下の力持ち」~
丹羽長秀は天文4年(1535年)、尾張国(現在の愛知県西部)に生まれました。織田信長より1歳年下で、若い頃から信長に仕え、その才能を早くから発揮します。通称は五郎左衛門、または五郎左(ごろうざ)です。
信長からの信頼は非常に厚く、重要な戦いや内政に数多く携わりました。特筆すべきは、安土城の普請奉行(ふしんぶぎょう)という大役を任されたことです。
普請奉行とは、城の建設における総責任者のことで、現代で言えば大規模プロジェクトのリーダーといったところでしょうか。
信長の壮大な構想を実現するため、資材調達から人員配置まで、その辣腕を振るったと言われています。
また、長秀は織田家臣団の中で、「木綿藤吉(もめん とうきち)、米五郎左(こめ ごろうざ)、掛かれ柴田(かかれ しばた)、退き佐久間(のき さくま)」と評されました。
これは、それぞれの武将の特徴を捉えたもので、藤吉郎(後の豊臣秀吉)は木綿のように丈夫で実用的、柴田勝家は勇猛果敢な攻撃型、佐久間信盛は慎重な撤退戦が得意、そして丹羽長秀は米のように誰からも好かれ、なくてはならない存在とされました。
この「米五郎左」という呼び名には、彼の温厚な人柄と、組織運営における不可欠な役割が集約されています。まさに、織田家という巨大組織を支える「縁の下の力持ち」だったのです。
一説では、信長は長秀のことを「友であり、兄弟である」とまで評したと言われています。
これは、家臣に対して厳しい評価を下すことが多かった信長にしては、異例の言葉です。長秀の誠実な人柄と、高い実務能力がいかに信長に評価されていたかがうかがえます。
歴史の転換点における丹羽長秀の動向
丹羽長秀は、その長いキャリアの中で数々の重要な歴史的局面に立ち会っています。
本能寺の変と山崎の戦い
天正10年(1582年)、本能寺の変で信長が横死した際、長秀は織田信孝(のぶたか)(信長の三男)と共に大坂で四国攻めの準備をしていました。
信長の死を知ると、即座に信孝を助けて備中高松城から中国大返しで戻ってきた羽柴秀吉(はしば ひでよし)と合流し、明智光秀を討つための山崎の戦いに参戦します。
この時、長秀は京都に近い場所にいた織田家の重臣の一人であり、その迅速な行動は秀吉にとって大きな力となりました。歴史の大きな転換点において、的確な判断を下せる人物だったと言えるでしょう。
清洲会議での役割
光秀を討った後、織田家の後継者問題と遺領配分を決定するために開かれたのが清洲会議(きよす かいぎ)です。
この会議で、長秀は池田恒興(いけだ つねおき)と共に秀吉を支持し、信長の孫である三法師(さんぽうし)(後の織田秀信(ひでのぶ))を後継者として擁立することに貢献しました。
これにより、秀吉が織田家中で主導権を握る大きなきっかけとなりました。この会議での長秀の立場は、秀吉のその後の台頭に大きな影響を与えたと言われています。
賤ヶ岳の戦い
その後、秀吉と柴田勝家との対立が深まり、天正11年(1583年)に賤ヶ岳(しずがたけ)の戦いが勃発します。
この戦いで長秀は秀吉方に与し、近江国(現在の滋賀県)の海津城を守備し、柴田軍の背後を牽制する役割を担ったとされています。
また、一説には、佐久間盛政(さくま もりまさ)軍に苦戦する秀吉軍に対し、琵琶湖の湖上輸送を駆使して兵糧や兵員を補給するなど、後方支援で大きく貢献したとも言われています。ここでも「米五郎左」の本領が発揮されたのかもしれません。
丹羽長秀と豊臣兄弟~盟友・秀吉との絆、そして秀長との関わり~
丹羽長秀の生涯を語る上で、豊臣秀吉とその弟・秀長(ひでなが)との関係は欠かせません。
豊臣秀吉との関係
長秀と秀吉は、信長配下の同僚として、長年にわたり苦楽を共にした仲です。
特に本能寺の変以降、長秀が一貫して秀吉を支持したことは、秀吉の天下取りにとって極めて大きな意味を持ちました。織田家譜代の重臣であり、温厚篤実な人柄で知られる長秀の支持は、秀吉の求心力を高める上で不可欠だったからです。
秀吉も長秀を深く信頼し、賤ヶ岳の戦いの後には、長秀に越前国(現在の福井県東部)と若狭国(現在の福井県南西部)を与え、若狭には国吉城、越前には北ノ庄城を拠点として123万石とも言われる広大な領地を任せました。
これは、秀吉政権下における長秀の重要性を示すものです。長秀は越前で検地を実施するなど、領国経営にも手腕を発揮しました。
しかし、晩年の長秀と秀吉の関係については、いくつかの説があります。
長秀は天正13年(1585年)に病死しますが、一説には、秀吉が次第に増長していく様に心を痛め、積聚(しゃくじゅ)(腹の腫物や寄生虫による病気と推測される)が悪化した際、その病巣を秀吉に送りつけ、「これで貴殿の天下取りの病も治るだろう」という趣旨の皮肉を込めた手紙と共に自刃した、という壮絶な逸話も伝わっています。
この逸話の真偽は定かではありませんが、二人の間に何らかの緊張関係が生じていた可能性を示唆するものとして、歴史ファンの間で語られることがあります。
ただ、一般的には病死説が有力とされています。
豊臣秀長との関係
一方、秀吉の弟である豊臣秀長と長秀の関係については、具体的な記録は多くありません。
しかし、天正2年(1574年)の長島一向一揆(ながしま いっこういっき)の際には、秀長や前田利家らと共に、長秀も先陣を切って戦ったとされています。
秀長は温厚で実直な性格で知られ、兄・秀吉を常に支え続けた人物です。その秀長と、同じく誠実さで知られた長秀は、戦場での共闘を通じて互いに信頼感を抱いていた可能性は十分に考えられます。
また、長秀の三男である仙丸(せんまる)(後の藤堂高吉(とうどう たかよし))は、秀吉の命令で秀長の家臣であった藤堂高虎(とうどう たかとら)の養子となっています。
これは、豊臣政権内における大名間の関係構築の一環であったと考えられますが、長秀と秀長・高虎との間に一定の関係性があったことをうかがわせるエピソードです。
丹羽長秀の最期と丹羽家のその後
前述の通り、丹羽長秀は天正13年(1585年)4月16日に病のため死去したとされています。享年51歳でした。
長秀の死後、家督は嫡男の丹羽長重(にわ ながしげ)が継ぎますが、丹羽家は波乱の道のりを歩むことになります。長重は秀吉の天下統一事業に従い、九州平定や小田原征伐にも参加しました。
しかし、秀吉の死後、関ヶ原の戦いでは西軍に与したため、戦後に改易(かいえき)(領地没収)されてしまいます。この時、加賀前田家預かりの身となりました。
一説には、長重は関ヶ原の戦いの前哨戦である浅井畷(あさいなわて)の戦いで東軍方の前田利長(まえだ としなが)軍を破る活躍を見せたにも関わらず、西軍の敗北により改易の憂き目にあったと言われています。この戦いでの勝利が逆に徳川家康の警戒を招いたという見方もあるようです。
しかし、長重はその後、大坂の陣で徳川方として戦功を挙げ、その実直な人柄も評価されたのか、常陸国古渡(ふるわたり)1万石を与えられて大名として復帰します。
さらに、その後も加増を重ね、最終的には陸奥国白河藩10万石余の大名となり、丹羽家は幕末まで存続しました。父・長秀が築いた「誠実さ」という無形の財産が、息子の代での再興に繋がったのかもしれません。
まとめ
丹羽長秀は、派手な武勇伝や奇抜な逸話は少ないものの、織田信長、豊臣秀吉という天下人に深く信頼され、その才覚を如何なく発揮した「万能型の武将」でした。
特に、その誠実な人柄と高い実務能力は、「米五郎左」という異名に象徴されるように、周囲から厚い信頼を寄せられました。
豊臣兄弟との関係においては、秀吉の天下取りを支える重要な役割を担い、その政権の安定に貢献しました。
彼の生涯は、現代社会に生きる私たちにとっても、組織の中でいかにして信頼を勝ち取り、貢献していくかという点で、多くの示唆を与えてくれるのではないでしょうか。
丹羽長秀という武将の生き様を通じて、戦国時代という時代の奥深さを改めて感じていただければ幸いです。








