- 戦国BANASHI TOP
- 歴史上の人物の記事一覧
- 戦国時代という激動の時代に、彗星(すいせい)のごとく現れ、日本の歴史を大きく塗り替えた男・織田信長
戦国時代という激動の時代に、彗星(すいせい)のごとく現れ、日本の歴史を大きく塗り替えた男・織田信長
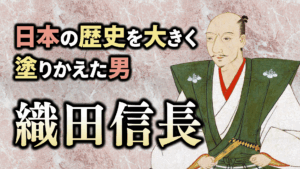
彼の名は、歴史ファンならずとも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
「うつけ者(奇抜な行動をする人、変わり者)」と呼ばれた若き日から、天下統一を目前にしながら本能寺に散るまで、その生涯はまさにドラマチックの一言に尽きます。
この記事では、そんな織田信長の魅力に迫ります。彼が成し遂げたこと、その人物像、そして、後の天下人・豊臣秀吉とその弟・秀長との関係など、歴史ファンが「もっと知りたい!」と思うポイントを、わかりやすく解説していきます。「信長って結局何がすごいの?」「秀吉とはどんな関係だったの?」そんな疑問にもお答えできるはずです。それでは、織田信長の知られざる世界へ、いざ出発しましょう!
目次
尾張の「うつけ者」から戦国の風雲児へ:信長、飛翔の序章
織田信長は、尾張国(おわりのくに:現在の愛知県西部)の戦国大名・織田信秀(おだのぶひで)の子として生まれました。幼名は吉法師(きっぽうし)。若い頃の信長は、奇抜な格好や行動で周囲を驚かせ、「尾張の大うつけ」と呼ばれていたことは有名な話です。しかし、それは既成概念にとらわれない、彼の型破りな発想の表れだったのかもしれません。
父・信秀の死後、家督を継いだ信長は、弟・信勝(のぶかつ)との家督争いを制し、尾張統一を進めます。この頃、美濃(みの:現在の岐阜県南部)の戦国大名・斎藤道三(さいとうどうさん)と聖徳寺で会見し、その器量を見抜かれたという逸話も残っています。道三は娘の濃姫(のうひめ)を信長に嫁がせており、この政略結婚が後の信長の勢力拡大に繋がったとも言われています。
桶狭間の戦い:信長、天下に名を轟かす
信長の名を天下に知らしめた最初の大きな戦いが、1560年の桶狭間の戦い(おけはざまのたたかい)です。駿河国(するがのくに:現在の静岡県中部・北東部)の大大名・今川義元(いまがわよしもと)が、2万5千とも4万5千ともいわれる大軍を率いて尾張に侵攻。対する信長軍はわずか数千。誰もが今川軍の勝利を疑いませんでした。
従来は世紀の大逆転劇として信長の軍事的才能と大胆不敵さを示す象徴的な出来事として取り上げられてきました。しかし、最近の研究によれば、織田軍は奇襲ではなく、正面から今川軍と戦い、義元は本陣になだれ込んだ織田軍に討ち取られたと言われています。
いずれにせよ、この戦いは彼の天下統一への大きな一歩となりました。もしこの戦いで信長が敗れていたら、日本の歴史は全く違うものになっていたかもしれませんね。
美濃攻略と「天下布武」:天下統一への意志
桶狭間の戦いの後、信長は美濃攻略に乗り出します。斎藤道三の死後、美濃を支配していたのは道三の子・龍興(たつおき)でしたが、信長は数々の困難を乗り越え、1567年、ついに稲葉山城(いなばやまじょう:後の岐阜城)を攻略し、美濃を手中に収めます。
この頃から、信長は「天下布武(てんかふぶ)」という印章を用い始めます。「武力をもって天下を統一する」という、彼の強い意志表示とされています。この「天下」が具体的にどこを指すのか(五畿内か日本全国か)については諸説ありますが、
最近の研究では室町幕府の再興を目指していたのではないかと考えられていて、さらなる研究が必要です。
破竹の進撃と立ちはだかる壁:信長包囲網
美濃を手に入れた信長は、1568年、室町幕府(むろまちばくふ)の再興を目指す足利義昭(あしかがよしあき)を奉じて上洛(じょうらく:京都へ行くこと)を果たします。これにより、信長は中央の政治にも大きな影響力を持つようになりました。しかし、その急激な台頭は、各地の戦国大名や寺社勢力の警戒心を煽ることにもなります。
姉川の戦いと比叡山焼き討ち:旧勢力との激突
越前国(えちぜんのくに:現在の福井県北東部)の朝倉義景(あさくらよしかげ)、近江国(おうみのくに:現在の滋賀県)の浅井長政(あざいながまさ)らは、信長に反旗を翻し、「信長包囲網」が形成されます。1570年の姉川の戦い(あねがわのたたかい)では、徳川家康(とくがわいえやす)の援軍を得て辛くも勝利を収めますが、戦いは一進一退を繰り返しました。
この包囲網の一角を担ったのが、強大な力を持つ宗教勢力、比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)でした。浅井・朝倉軍をかくまった延暦寺に対し、信長は1571年、容赦ない焼き討ちを行います。僧侶だけでなく、女性や子供も犠牲になったと言われ、この事件は信長の「非情さ」を示すエピソードとして語り継がれています。しかし、当時の寺社勢力が武装し、俗世の権力と結びついていたことも考慮に入れる必要があり、この焼き討ちの評価は現代でも意見が分かれるところです。一説には、焼き討ちの規模や内容について異なる見解も示されており、例えば建物の全焼は限定的だったという考古学的な調査結果を指摘する声もあります。この事件の真相については、さらなる研究が待たれる部分です。
天下統一への最終章と本能寺の悲劇
数々の苦難を乗り越え、信長は着実に天下統一への歩みを進めます。
長篠の戦いと安土城:新時代の幕開け
1575年の長篠の戦い(ながしののたたかい)では、当時最強と謳われた武田勝頼(たけだかつより)の騎馬隊に対し、信長は大量の鉄砲と馬防柵(ばぼうさく:馬の侵入を防ぐ柵)を用いた新戦術で圧勝します。この戦いは、戦国時代の戦術に大きな変革をもたらしたと言われています。もはや、個人の武勇よりも、組織力や兵器の運用が勝敗を左右する時代が到来したのです。
そして、1576年からは、琵琶湖のほとりに壮大な安土城(あづちじょう)の築城を開始します。五層七階(地上六階地下ー階とも)の天主(てんしゅ:一般に言う天守閣)を持ち、内部は狩野永徳(かのうえいとく)らによる豪華な障壁画で飾られたこの城は、信長の権威と新しい時代の到来を象徴するものでした。城下では楽市楽座(らくいちらくざ)という経済政策を実施し、商業の活性化も図りました。これは、現代でいう「規制緩和」に近いものかもしれませんね。
本能寺の変:夢潰え、歴史は変わる
天下統一を目前にした1582年6月2日、信長は京都の本能寺(ほんのうじ)で、信頼していた家臣の一人、明智光秀(あけちみつひで)の謀反(むほん)により自害に追い込まれます。享年49。「人間五十年、下天(げてん)のうちを比ぶれば、夢幻(ゆめまぼろし)の如くなり」という幸若舞(こうわかまい)「敦盛(あつもり)」の一節を好んだと言われる信長。その最期は、まさに夢幻のごとく、あまりにもあっけないものでした。
光秀がなぜ謀反を起こしたのか、その動機は今なお謎に包まれており、「怨恨説」「野望説」「黒幕説」など、様々な説が歴史ファンの間で議論されています。この事件がなければ、日本の歴史は大きく変わっていたでしょう。まさに、歴史のターニングポイントと言える大事件です。
先進性と多面性:織田信長という人物
織田信長は、ただ戦が強いだけの武将ではありませんでした。彼の政策や人物像には、時代を先取りするような先進性と、一言では語り尽くせない多面性が見られます。
革新的な政策の数々
信長は、旧来の慣習や権威にとらわれず、次々と新しい政策を打ち出しました。
- 楽市楽座:既得権益(きとくけんえき:特定の人が昔から持っている権利や利益)を排除し、自由な商業活動を奨励。経済の活性化を目指しました。
- 関所の撤廃:物流の妨げとなる関所を減らし、物資の流通をスムーズにしました。現代のTPP(環太平洋パートナーシップ協定)のような、自由貿易の精神に通じるものがあるかもしれません。
- 検地と兵農分離の試み:領地の正確な把握(検地)と、武士と農民の身分を明確に分ける兵農分離(へいのうぶんり)を進めようとしました。これは、後の豊臣秀吉による太閤検地(たいこうけんち)や刀狩(かたながり)へと繋がっていきますが、信長の段階ではまだ試行的であったという見方もあります。
- 鉄砲の大量運用:長篠の戦いで見せたように、新しい兵器を積極的に導入し、戦術を革新しました。
これらの政策は、信長の中央集権的な国家構想の実現に向けた布石であったと考えられています。
「第六天魔王」の素顔
信長は、比叡山焼き討ちなど、敵対する者には容赦ない一面を見せたことから、「第六天魔王(だいろくてんまおう)」と恐れられていました。しかし、一方で、家臣の能力を重視する実力主義を貫き、身分にとらわれず有能な人材を登用したことでも知られています。また、南蛮文化(なんばんぶんか:当時のヨーロッパ文化)に強い関心を示し、キリスト教を保護したり、西洋の技術や知識を積極的に取り入れたりもしました。
茶の湯(ちゃのゆ)を愛し、名物茶器を収集して家臣への褒美(ほうび)に使うなど、文化的な側面も持ち合わせていました。彼の行動は、時に冷酷非情に見えても、その裏には天下統一という大きな目的と、新しい時代を切り開こうとする強い意志があったのかもしれません。
信長と豊臣兄弟:天下取りのバトンは渡されたのか?
織田信長の家臣団の中でも、特に異彩を放っていたのが、後の天下人・羽柴秀吉(はしばひでよし)、すなわち豊臣秀吉です。そして、その秀吉を陰に陽に支えたのが、弟の豊臣秀長(とよとみひでなが)でした。信長とこの兄弟の関係は、歴史を大きく動かす要因の一つとなります。
羽柴秀吉:猿と呼ばれた男の成り上がり
秀吉は、低い身分から信長に仕え、その才能と機転で頭角を現しました。信長の草履(ぞうり)を懐(ふところ)で温めたという有名な逸話(真偽は不明)や、一夜にして城を築いたとされる「墨俣一夜城(すのまたいちやじょう)」の伝説(これも史実かどうかは議論があります)など、彼の出世物語は枚挙にいとまがありません。
信長は、秀吉の明るい性格や人懐っこさ、そして何よりもその実行力を高く評価していたと言われています。金ヶ崎の退き口(かねがさきののきくち)では、殿(しんがり:退却する軍の最後尾で敵の追撃を防ぐ部隊)という最も危険な任務を秀吉に任せ、見事成功させています。その後も、中国方面軍の司令官として、毛利氏(もうりし)との戦いで大きな功績を挙げました。
信長は秀吉を「猿」や「禿げ鼠(はげねずみ)」などと呼んだという記録も残っており、そこにはある種の親しみと、同時にどこか侮れない存在としての認識があったのかもしれません。秀吉の才能を認めつつも、その底知れぬ野心を見抜いていた可能性も否定できません。
豊臣秀長:兄・秀吉を支えた「大和宰相(やまとさいしょう)」
秀吉の弟・秀長は、派手な兄とは対照的に、温厚篤実(おんこうとくじつ:穏やかで誠実な人柄)で、優れた調整能力を持つ人物だったと言われています。信長政権下では、主に秀吉の補佐役として活動し、兄の軍事行動を支えました。例えば、秀吉が中国攻めを担当した際には、秀長も但馬国(たじまのくに:現在の兵庫県北部)の平定などで活躍しています。戎光祥出版の『図説 豊臣秀長』の目次によれば、信長の馬廻(うままわり:主君の側近警護の武士)として登場し、信長の訃報に接するまでの動向も記されているようです。
信長から秀長への直接的な評価を示す史料は多くありませんが、秀吉が重要な任務を任される中で、その片腕として秀長が機能していたことは、信長も認識していたはずです。秀吉が「攻め」の武将なら、秀長は「守り」や「調和」の武将であり、この兄弟の絶妙なコンビネーションが、後の豊臣政権の安定に大きく貢献することになります。
秀長は後に大和国(やまとのくに:現在の奈良県)を与えられ、その善政から「大和宰相」と称えられました。もし秀長がいなければ、秀吉の天下統一も、あるいはその後の豊臣政権の運営も、もっと困難なものになっていたかもしれません。
本能寺の変、そして兄弟の決断
本能寺の変で信長が討たれたという報せは、備中高松城(びっちゅうたかまつじょう)で毛利氏と対峙していた秀吉・秀長兄弟のもとにも届きます。この絶体絶命の状況で、秀吉は驚くべき速さで毛利氏と和睦し、京都へ引き返す「中国大返し(ちゅうごくおおがえし)」を敢行。そして、山崎の戦い(やまざきのたたかい)で明智光秀を討ち、主君の仇(かたき)を討つという大義名分を手にします。この時、秀長も兄を補佐し、軍勢を率いて奮戦したと言われています。
その後、信長の後継者を決める清洲会議(きよすかいぎ)を経て、秀吉は織田家内部での影響力を強めていきます。そして、信長の筆頭家老であった柴田勝家(しばたかついえ)との対立が深まり、1583年の賤ヶ岳の戦い(しずがたけのたたかい)で激突。この戦いでも秀長は重要な役割を果たし、秀吉軍の勝利に貢献したとされています。一説には、秀長は柴田勝家の甥・柴田勝政(しばたかつまさ)を討ち取るなどの活躍を見せたとも言われていますが、具体的な軍功についてはさらなる研究が必要です。この勝利により、秀吉は信長の後継者としての地位を不動のものとし、天下統一へと大きく前進するのです。
信長から秀吉、そして秀長へ。直接的な後継指名があったわけではありませんが、信長の死という未曾有(みぞう)の事態の中で、豊臣兄弟がその遺業を引き継ぐ形で歴史の表舞台に躍り出たことは間違いありません。
織田信長の遺産:日本史における意義と後世への影響
織田信長は、志半ばで倒れましたが、彼が日本の歴史に残した影響は計り知れません。
信長は、中世的な権威や秩序を大胆に破壊し、新しい時代の扉を開きました。彼の行った中央集権化の試みや経済政策、軍事改革は、その後の豊臣秀吉による天下統一事業、さらには江戸幕府による安定した統治体制へと繋がる基礎を築いたと言えます。もし信長がいなければ、戦国乱世はさらに長引き、近代日本の夜明けはもっと遅れていたかもしれません。
また、信長の劇的な生涯や型破りな人物像は、後世の人々を魅了し続けています。「革新的な英雄」「冷酷非情な独裁者」「謎多きカリスマ」など、様々な評価がなされ、小説、映画、ドラマ、ゲームなど、数多くの創作物の題材となってきました。現代においても、彼のリーダーシップや決断力、先見性などは、ビジネスの世界などでも参考にされることがあります。
織田信長という人物をどう評価するかは、人それぞれかもしれません。しかし、彼が日本の歴史に強烈なインパクトを与え、大きな変革をもたらした「時代の寵児(ちょうじ)」であったことは、誰もが認めるところでしょう。
まとめ:織田信長から学ぶこと
織田信長の生涯を駆け足で見てきましたが、いかがでしたでしょうか。古い殻を打ち破り、新しい時代を築こうとした彼の情熱、困難に立ち向かう勇気、そして天下を見据える壮大なビジョンは、現代を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれます。
特に、豊臣兄弟との関係は、リーダーシップや組織論、人間関係といった観点からも興味深いものがあります。信長が秀吉の才能を見抜き、育て上げ、そして秀吉がその期待に応え、さらには弟・秀長という最高のパートナーと共に天下を掴み取っていく様は、まさに歴史のダイナミズムを感じさせます。
織田信長。彼の生き様は、これからも多くの歴史ファンを惹きつけ、語り継がれていくことでしょう。この記事が、あなたが織田信長という人物、そして彼が生きた戦国時代への興味を深める一助となれば幸いです。
編集者:寺中憲史








