- 戦国BANASHI TOP
- 歴史上の人物の記事一覧
- 歴史の渦に消えた若き龍、斎藤龍興の悲運と執念
歴史の渦に消えた若き龍、斎藤龍興の悲運と執念
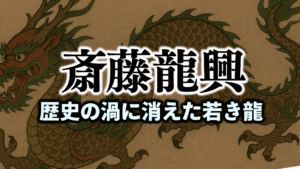
目次
歴史の渦に消えた若き龍、斎藤龍興の悲運と執念
戦国時代、美濃国(現在の岐阜県南部)を舞台に、祖父・斎藤道三、父・斎藤義龍と続いた斎藤氏の最後の当主、それが(さいとう たつおき)です。若くして家督を継ぎ、強大な織田信長の勢力と対峙し、やがて国を追われ、流転の末に非業の最期を遂げた悲劇の武将として知られています。しかし、近年の研究では、単なる「暗愚な君主」というレッテルだけでは語れない、龍興の新たな側面も浮かび上がってきました。本記事では、斎藤龍興の生涯を追いながら、その実像と、旧臣たちの動向にも光を当てていきます。
若き当主の誕生と美濃の揺らぎ
斎藤龍興は天文17年(1548年、諸説あり)、斎藤義龍の嫡男として生まれました。「マムシ」の異名を第二次世界大戦後につけられた斎藤道三を祖父に持ちます。父・義龍は弘治2年(1556)に勃発した、道三との壮絶な親子喧嘩である長良川合戦を経て美濃国主の座を確固たるものにしました。そして永禄2年(1559年)には、室松幕府から将軍家に連なる足利一門の格式の高い血筋である一色姓へと改姓しています。永禄4年(1561年)、病により35歳という若さで急逝してしまいます。これにより、龍興はわずか14歳という若さで斎藤家の家督を相続することとなりました。
家督相続直後から、美濃には隣国尾張の織田信長からの圧力が強まります。同年5月には、信長が木曽川を越えて西美濃に侵攻し、森部合戦が勃発。この戦いで斎藤方は重臣の日比野清実らを失うなど、苦戦を強いられます。さらに永禄5年(1562年)には有力家臣であった郡上八幡城主・遠藤盛数が病没するなど、若き龍興の前途には暗雲が立ち込めていました。ただ同年2月に織田・斎藤間で和睦が成立しており、龍興はひとまず安息を得ています。
暗愚か、悲運か?龍興の素顔と統治
斎藤龍興は、後世の創作物や一部史料において、「暗愚な君主」「酒色に溺れ、佞臣を重用した」といった評価がなされることが少なくありません。『甫庵信長記』や『老人雑話』などがその代表例です。確かに、若年で当主となった龍興には、経験豊富な父・義龍ほどの統率力や政治手腕を発揮することは難しかったかもしれません。
しかし、歴史学者・木下聡氏などの研究では、これらの評価は織田信長や、後に龍興を諌めるために稲葉山城を乗っ取った竹中半兵衛の功績を際立たせるために、過度に低くされた可能性があると指摘されています。龍興は信長の猛攻に対し、美濃三人衆などの有力家臣の離反(永禄10年)まで、約6年間も持ちこたえており、決して無能ではなかったと考えられます。また、甲斐の武田信玄との同盟を模索したり、足利将軍家から「義」の字と「龍」に代わる「棟」の字(一色義棟)を賜って名を改めるなど、外交や権威付けの努力も見られます。
興味深いエピソードとしては、ルイス・フロイスの『日本史』において、龍興自身、またはその義弟が宣教師ガスパル・ヴィレラと宗教問答を行った記録が残っており、当時の龍興がキリスト教に関心を示していた可能性がうかがえます。龍興はヴィレラに対し、「なぜこの世は戦乱が絶えず、善人が報われないのか」といった根源的な問いを発したとされています。これは、彼が置かれた厳しい状況と内面の葛藤を反映しているのかもしれません。
稲葉山城の衝撃と信長の影
龍興の治世において、その権威を大きく揺るがす事件が発生します。永禄7年(1564年)、家臣の竹中半兵衛重治が、その舅である安藤守就(西美濃三人衆の一人)と共謀し、わずかな手勢で龍興の居城・稲葉山城(後の岐阜城)を占拠したのです。
この前代未聞の乗っ取りの動機については諸説ありますが、一般的には、龍興の行状を諌めるためであったとされていますが、半兵衛の生きていた時代より遠くない時期に記された書には、半兵衛が主君を戒めるために占拠したとする史料は見当たりません。おそらく、羽柴秀吉の「軍師」である半兵衛を理想化していく中で生み出されたと思われます。半兵衛は、龍興やその側近から侮辱を受けるなど名誉を傷つけられたと、半兵衛の生きていた時代に近い書には記されています。半兵衛は半年ほど城を占拠した後、信長からの誘いを断り、龍興に城を返還して居城へ戻った。しかし、この事件は龍興の求心力低下を内外に露呈する結果となり、領国内の領主たちの動揺を加速させました。
そして永禄10年(1567年)、織田信長の執拗な美濃侵攻は最終局面を迎えます。信長の調略により、西美濃三人衆と呼ばれた稲葉良通(一鉄)、安藤守就、氏家直元(卜全)が織田方に内応。これにより斎藤勢は一気に崩壊し、龍興は稲葉山城を追われ、木曽川を下って伊勢長島へと逃亡したといいます。この時、龍興はまだ21歳でした。ここに、道三以来三代続いた美濃斎藤氏は、事実上滅亡したのです。
流転の日々と反信長への執念
美濃を失った龍興でしたが、その執念は衰えませんでした。その後、伊勢長島から畿内に赴き、三好三人衆ら反信長勢力と合流したと思われます。永禄12年(1569)に、三好三人衆が本圀寺(ほんこくじ)にいる足利義昭を襲撃した時、龍興もその軍の中にいたといいます。
しかし、各地の反信長勢力も次第に劣勢となっていきます。龍興は新たな活路を求め、越前国の朝倉義景を頼りました。義景は信長包囲網の有力な一角であり、龍興は客将として迎えられたと考えられます。
豊臣兄弟との交錯――龍興旧臣たちのその後
斎藤龍興の没落と入れ替わるように台頭してきたのが、織田信長の家臣であった羽柴秀吉(豊臣秀吉)とその弟・秀長です。美濃攻略戦は、秀吉が信長の家臣団の中で頭角を現す重要な契機となりました。
羽柴秀吉と美濃攻略:
秀吉の美濃攻略における最も有名な逸話は「墨俣一夜城」の伝説でしょう。永禄9年(1566年)、秀吉(当時は木下藤吉郎)が墨俣に砦を築き、これを拠点として美濃攻略を大きく前進させたとされます。一夜で城を築いたというのは後世の創作ではあり、このとき墨俣に砦を構えていなかった可能性も高いです。しかし、秀吉が国境周辺に戦略的に重要な拠点を確保し、美濃攻撃の橋頭保としたことは事実のようです。稲葉山城の最終攻略においては、秀吉が調略を担当し、城の裏手から兵を導き入れたという話や、「千成瓢箪」の馬印を掲げ始めたのもこの頃からという話も伝わっています。
羽柴秀長と美濃攻略:
一方、弟の秀長(当時は小一郎)は、この時期の具体的な戦功は兄ほど目立ってはいませんが、秀吉が出陣する際の城の留守居役を務めるなど、後方支援で兄を支えていたとされています。
龍興旧臣たちの道:
斎藤氏滅亡後、龍興の旧臣たちの多くは、新たな主君を求めて離散しました。その中には、後に豊臣政権下で活躍する人物も少なくありません。
- 竹中半兵衛重治:斎藤家滅亡後、秀吉に三顧の礼で迎えられたといわれ、信長の天下一統事業に貢献しました。しかし、病には勝てず、陣中で若くして亡くなりました。
- 稲葉良通(一鉄):西美濃三人衆の一人で、信長に降った後、その家臣として各地を転戦。本能寺の変後しばらくして秀吉に仕え、その子・貞通も豊臣氏家臣として活躍しました。
- 日根野弘就:龍興に仕えた後、信長、そして秀吉に仕え、各地の戦役で武功を挙げました。
- 加藤光泰:龍興に仕えた後、秀吉の家臣となり、甲斐国主にまで出世しました。文禄の役で朝鮮にて病没。
- 氏家氏:氏家直元(卜全)は信長に仕えましたが早くに戦死。その子・行広や行継は、後に秀吉に仕えました。
- 不破光治:斎藤氏滅亡後信長に降り、府中三人衆の一人として越前統治に関わりました。その子・直光は前田利家に仕え、秀吉とも関わりを持ちました。
- 長井氏の末裔:龍興の大叔父にあたる長井道利は最後まで龍興と共に戦いましたが、その一族(井上氏を称す)からは後に秀吉に仕える者も出ました。
- 安藤守就:信長に仕えましたが、後に追放され、本能寺の変後に稲葉一鉄と戦って敗死。その一族の豊臣政権下での動向は複雑です。
- 遠藤慶隆:龍興に仕え、斎藤氏滅亡後は信長に仕えました。本能寺の変後は秀吉に仕えるも、天正16年(1588)に本領を没収されます。その後、関ヶ原合戦で東軍に属し、その功で旧領を回復しました。
これらの旧臣たちの動向は、主家滅亡後の武士たちが、いかにして激動の時代を生き抜こうとしたかを示す好例と言えるでしょう。特に、竹中半兵衛や稲葉一鉄のように、新たな主君のもとでその才能を開花させた者もいれば、時代の波に翻弄された者もいました。龍興の失った美濃は、信長、そして秀吉にとって天下統一への重要な足がかりとなったのです。
刀根坂の露と消ゆ――龍興、最後の戦い
越前の朝倉義景のもとに身を寄せていた龍興でしたが、天正元年(1573年)、ついに最期の時が訪れます。信長は破竹の勢いで越前に侵攻。朝倉軍は総崩れとなり、義景は逃亡します(後に自害)。
龍興は、この絶望的な状況下で朝倉軍の一員として奮戦します。同年8月、近江国境に近い刀根坂(現在の福井県敦賀市)で行われた織田軍との激戦(刀根坂の戦い)において、龍興は、朝倉方の将兵である山崎吉家、河井宗清らと共に壮絶な討死を遂げました。享年26(または27)。その首は京都に送られ、獄門にかけられたと伝わります。
一説には、龍興は刀根坂で死なず、越中(富山県)に逃れて僧となり「九右ェ門」と名乗り、温泉を発見して「霊鶴温泉」を開いたという伝説も残っていますが、これはあくまで伝説の域を出ません。
結び――斎藤龍興再考
斎藤龍興の生涯は、戦国という非情な時代の波に翻弄された、若き当主の悲劇の物語として語られます。祖父や父が築き上げたものを守り切れず、国を失い、若くして散ったその運命は、多くの同情を誘います。「暗愚」という従来の評価に対し、近年の研究は、彼が置かれた困難な状況や、彼なりに抵抗を試みた点を評価する動きも見られます。
龍興の旧臣たちが、後に豊臣秀吉のもとで活躍したことは、歴史の皮肉とも言えるかもしれません。龍興の物語は、単なる敗者の記録としてではなく、戦国時代の武将たちの多様な生き様、そして時代の大きなうねりを理解するための一つの視点を与えてくれます。彼の短い生涯と、その後の家臣たちの運命は、今もなお私たちに多くのことを語りかけているのです。
▼主な参考文献
木下聡『斎藤氏四代』(ミネルヴァ書房、2020年)
柴裕之・小川雄編『戦国武将列伝6』(戎光祥出版、2024年)
『日本人名大辞典』、『国史大辞典』
編集者:相模守








