- 戦国BANASHI TOP
- 歴史上の人物の記事一覧
- 知将・筒井順慶の実像~洞ヶ峠だけじゃない!織田・豊臣政権を生き抜いた大和の盟主~
知将・筒井順慶の実像~洞ヶ峠だけじゃない!織田・豊臣政権を生き抜いた大和の盟主~
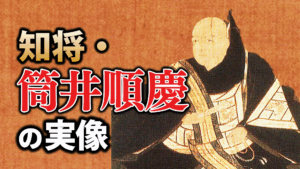
歴史の教科書や時代劇では、時に「洞ヶ峠(ほらがとうげ)の日和見(ひよりみ)」という言葉と共に語られることのある筒井順慶(つついじゅんけい)。
しかし、その一面的なイメージだけで彼を語るのは、あまりにもったいないです。彼は、戦国時代の荒波の中、知略と決断力で大和国(やまとのくに、現在の奈良県)をまとめ上げ、織田信長、そして豊臣秀吉という天下人に仕え、その短い生涯を駆け抜けた人物です。この記事では、そんな筒井順慶の知られざる実像に迫ります。
目次
筒井順慶とは何者か?~大和国の名門、苦難の始まり~
筒井順慶は、天文18年(1549年)、大和国の有力な国人(こくじん、その土地の有力武士)である筒井順昭(じゅんしょう)の子として生まれました。筒井氏は、興福寺(こうふくじ)の衆徒(しゅと、寺院に所属する僧兵や武士)を母体とする由緒ある家柄で、大和国に大きな影響力を持っていました。
しかし、順慶の人生は波乱の幕開けとなります。父・筒井順昭が天文19年(1550年)に28歳(数え年。当時の平均寿命を考えると若くしての死去でした)で病死したため、順慶はわずか2歳(数え年)で家督を相続することになります。
一説によれば、順昭は自身の死を1年間隠し、瓜二つの影武者(黙阿弥、もくあみ)木阿弥を立てて家中の動揺を抑え、幼い順慶の地盤を固めようとしたと伝えられています。
「元の黙阿弥」木阿弥という言葉の語源になったとも言われるこの逸話は、当時の筒井家が置かれた厳しい状況を物語っているのかもしれません。
若き当主の行く手には、戦国時代という混沌と、そして最大の宿敵・松永久秀(まつながひさひで)との長い戦いが待ち受けていました。
松永久秀との死闘~大和国を巡る攻防と逆転劇~
筒井順慶の生涯を語る上で欠かせないのが、梟雄(きょうゆう、残忍で勇猛な人物)・松永久秀との十数年に及ぶ死闘です。
久秀は、三好長慶(みよしながよし)の家臣から頭角を現し、やがて大和国を我が物にしようと画策。若い順慶にとって、久秀はまさに巨大な壁として立ちはだかりました。
永禄年間(1558年~1570年)を通じて、筒井城(つついじょう)を巡る攻防は何度も繰り返されました。
順慶は、松永軍の猛攻により筒井城を追われるなど、苦しい戦いを強いられます。時には一族の元へ落ち延び、再起を期す日々も送りました。まるで、現代のベンチャー企業が巨大資本のライバル企業に挑むような、厳しい戦いだったと言えるでしょう。
しかし、順慶はただ守勢に回っていただけではありません。三好三人衆(みよしさんにんしゅう)と結んで久秀に対抗したり、ゲリラ戦術を駆使したりと、知略を尽くして抵抗を続けます。
そして元亀2年(1571年)、辰市城の戦い(たついちじょうのたたかい)で、ついに松永・三好連合軍を破るという大きな勝利を手にします。
この勝利は、長らく続いた久秀との力関係を逆転させる大きな転換点となりました。
織田信長との出会いと大和国平定~信頼を勝ち取った武将~
辰市城の戦いで勢いづいた順慶は、中央で急速に力を伸ばしていた織田信長(おだのぶなが)に接近します。
、天正2年(1574年)、他の織田家臣とともに、年頭の挨拶を行いました。これが信長との初対面と見られ、これにより正式に信長に臣従しました。参考文献:金松誠『シリーズ・実像に迫る019 筒井順慶』戎光祥出版 2019
当時、信長と対立していた松永久秀を牽制(けんせい)する意味でも、この臣従は重要な意味を持ちました。一説には、後の明智光秀(あけちみつひで)の斡旋(あっせん)があったとも言われています。
信長の家臣となった順慶は、その期待に応える働きを見せます。天正4年(1576年)には、信長から大和国の守護に任ぜられ、名実ともに大和国の支配者としての地位を確立。
そして翌天正5年(1577年)、信長に反旗を翻した松永久秀を信貴山城(しぎさんじょう)にで攻め滅ぼし、長年の宿敵との戦いに終止符を打ちました。
この時、久秀が名器・平蜘蛛(ひらぐも)の茶釜と共に爆死したという逸話は有名ですが、その陰には順慶の長年の苦闘があったのです。
信長の信頼を得た順慶は、その後も石山本願寺(いしやまほんがんじ)攻めや播磨(はりま)攻めなど、各地の戦いに参陣。
天正8年(1580年)には、信長の命令により本城以外の城を破却する「一国一城令」に先駆けたような形で、居城を筒井城から新たに築城した大和郡山城(やまこおりやまじょう)へ移し、大和国の支配体制を強化しました。
この郡山城への移転は、低湿地にあった筒井城の弱点を克服し、より強固な支配拠点を築くという、順慶の先見性を示すものだったのかもしれません。
本能寺の変と洞ヶ峠~「日和見」の真相と苦渋の決断~
天正10年(1582年)6月2日、日本史を揺るがす大事件、本能寺の変(ほんのうじのへん)が勃発します。主君・織田信長が明智光秀に討たれたという報は、順慶にも大きな衝撃を与えました。
光秀は、順慶にとって信長への臣従を仲介した恩人であり、縁戚関係にもあったと言われています。当然、光秀は順慶の加勢を期待しました。
この時、順慶がどちらに味方するか態度を決めかねて洞ヶ峠に布陣し、戦況を傍観したというのが、いわゆる「洞ヶ峠の日和見」という俗説です。「洞ヶ峠を決め込む」という言葉は、ここから生まれたとされています。
しかし、近年の研究ではこの俗説に疑問が呈されています。
『多聞院日記(たもんいんにっき)』などの史料によれば、順慶は光秀の誘いを拒否し、居城である大和郡山城で籠城の準備を進めていたとされています。実際に洞ヶ峠に布陣したのは、順慶の加勢を待つ光秀軍だったという説が有力です。
当時の状況を考えれば、順慶の判断は決して単純な日和見ではなかったでしょう。
畿内(きない、近畿地方の中心部)の情勢は混沌とし、どちらが勝利を収めるか予断を許さない状況でした。
情報が錯綜(さくそう)する中、軽率な行動は自らの破滅を招きかねません。順慶は、大和国と家臣領民を守るため、冷静に情報を収集し、最善の道を選ぼうとしたのではないでしょうか。
結果的に、羽柴秀吉(はしばひでよし、後の豊臣秀吉)に恭順(きょうじゅん)の意を示しますが、その判断はまさに生き残りをかけた苦渋の決断だったと言えるでしょう。
豊臣政権下での筒井順慶~秀吉・秀長との関係と大和の安寧~
山崎の戦いで明智光秀を破った羽柴秀吉は、天下統一への道を突き進みます。順慶は、秀吉の元に参じますが、山崎の戦いに直接参加しなかったことなどを理由に、秀吉から厳しい叱責(しっせき)を受けたと伝えられています。
しかし、結果的には大和国の所領は安堵(あんど、領地支配を認められること)されました。秀吉にとって、大和国を安定させる上で順慶の力は依然として重要だったのでしょう。
その後、順慶は秀吉の配下として、天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦い(しずがたけのたたかい)では、秀吉が畿内の城を固める際に人質を差し出した武将の一人として記録されています。
また、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦い(こまき・ながくてのたたかい)にも病を押して出陣し、伊勢(いせ)や美濃(みの)を転戦しました。
豊臣政権において、特に重要なのが秀吉の弟である豊臣秀長(とよとみひでなが)との関係です。
秀吉は、弟の秀長を信頼し、畿内の重要拠点である大和国を任せる構想を持っていました。
順慶の死後、天正13年(1585年)に秀長が大和国主として大和郡山城に入り、大和・和泉(いずみ)・紀伊(きい)三国などで100万石を超える所領を持つ大大名となりました。
この際、順慶の養子・定次(さだつぐ)は伊賀国(いがのくに、現在の三重県西部)へ移封(いほう、領地替え)されました。
これは、豊臣政権による中央集権化の一環であり、順慶が生きていればどのような動きを見せたのか、歴史のIFを想像させる出来事です。
一説には、秀長は順慶の廟所(びょうしょ、墓所)や筒井城の跡地を寺社に寄進するなど、前領主である順慶に配慮した政策を行ったとも伝えられています。このあたりからも、豊臣政権が順慶の実績を一定評価していた可能性がうかがえます。
知将・順慶の内政手腕と文化的素養~戦いだけではない魅力~
筒井順慶は、優れた武将であっただけでなく、内政家、文化人としても注目すべき側面を持っています。
大和郡山城への移転と城下町の整備は、その代表例です。
信長の命を受け、また戦略的な必要性から郡山に新たな拠点を築いた順慶は、城下町の発展にも力を注いだと考えられます。
後に豊臣秀長が郡山城を大改修し、本格的な城下町経営(「箱本十三町」の設置や楽市楽座など)を行いますが、その基礎には順慶の整備があったと言えるでしょう。
ただし、具体的な順慶の政策については史料が乏しく、秀長の業績との切り分けが今後の研究課題とされています。
また、順慶は寺社との関係にも苦心しました。
大和国は興福寺や東大寺(とうだいじ)など、古来より力を持つ寺社が多い土地柄です。信長政権下では、鉄砲鋳造のために寺社の釣鐘(つりがね)を供出させたり、興福寺の僧侶を処罰したりするなど、厳しい姿勢で臨むこともありました。
一方で、自身も元は興福寺の衆徒であり、仏教への信仰も篤く、寺社への寄進も行っています。この複雑な関係性は、当時の大和国統治の難しさを物語っています。
文化人としての順慶も見逃せません。彼は茶の湯を深く愛し、名物茶器「筒井筒(つついづつ)」にまつわる逸話は有名です。
この茶碗は、元は順慶が所持していましたが、本能寺の変後、明智光秀に渡り、その後秀吉の手に渡ったとされています。
また、能楽(のうがく)にも造詣が深く、自ら演じることもあったと言われています。
こうした文化的素養は、戦国の世にあって彼の人間的な幅広さを示しており、多くの武将や文化人と交流を持つ上でも役立ったのかもしれません。
家臣団との関係では、特に島左近(しまさこん、島清興)の存在が知られています。
左近は、順慶の死後、筒井家を離れますが、後に石田三成(いしだみつなり)に仕え、関ヶ原の戦い(せきがはらのたたかい)で勇名を馳せました。
順慶の下で、左近がどのように活躍し、どのような関係を築いていたのか、詳細は不明な点も多いですが、後の名将を育てた土壌が筒井家にあったことは確かでしょう。
→補足:天正十一年(1583年)の賤ヶ岳の戦いの際、織田信雄の家臣が信孝側についた国人の攻撃にあったため、救援に向かいに伊賀へ出陣しましたが、その道中夜討ちに遭い多数の死傷者を出してしまいました。『多聞院日記』に夜討ちで負傷した順慶の家臣が記録されていますが、その中に嶋左近の名があります。嶋家は元は大和椿井(平群町)を本拠とする国人であり、筒井家臣としてこの頃台頭しています。参考文献:金松誠『シリーズ・実像に迫る019 筒井順慶』戎光祥出版 2019
若すぎる死と、その後の筒井家~受け継がれなかった志~
小牧・長久手の戦いから大和へ帰還した筒井順慶でしたが、長年の激務が祟ったのか、病状が悪化。天正12年(1584年)8月11日、わずか36歳という若さでこの世を去りました。
死因は胃癌(いがん)であったとする説が有力です。「根は枯れじ 筒井の水の清ければ 心の杉の葉は浮かぶとも」という辞世の句を残したと伝えられています。
順慶の死後、養子の定次が家督を継ぎますが、前述の通り伊賀へ移封。
その後、定次は関ヶ原の戦いでは東軍に属したものの、江戸時代に入ってから豊臣氏に内通した疑いなどをかけられ、改易(かいえき、領地没収・武士の身分剥奪)されてしまいます。
これにより、戦国大名としての筒井氏は歴史の表舞台から姿を消すことになりました。
もし順慶が長生きしていれば、豊臣政権下でどのような役割を果たしたのか、そして筒井家の運命はどう変わっていたのか。歴史に「もし」はありませんが、彼の早すぎる死は、多くの人々に惜しまれたことでしょう。
まとめ~筒井順慶、再評価されるべき知将~
筒井順慶の生涯を振り返ると、「洞ヶ峠の日和見」という一面的なイメージだけでは捉えきれない、複雑で魅力的な人物像が浮かび上がってきます。
幼くして家督を継ぎ、松永久秀という強大な敵と渡り合い、織田信長、豊臣秀吉という天下人に仕えながら大和国を守り抜いたその手腕は、まさに「知将」と呼ぶにふさわしいものです。
本能寺の変における判断も、単なる日和見ではなく、激動の時代を生き抜くためのリアリストとしての苦渋の決断であった可能性が高いと言えます。
内政においては、大和郡山城への移転など、国の将来を見据えた政策を行い、文化人としても茶の湯や能楽を愛するなど、多才な一面も持っていました。
筒井順慶という武将は、派手な武勇伝や天下取りの野望といったイメージとは異なるかもしれませんが、自らが置かれた状況の中で最善を尽くし、困難を乗り越えていった人物です。
この記事をきっかけに、彼の生き様や知略、そして人間的な魅力に、改めて光が当てられることを願っています。
編集者:寺中憲史








